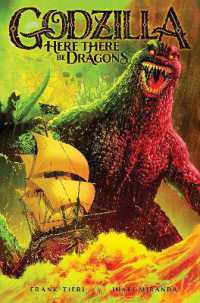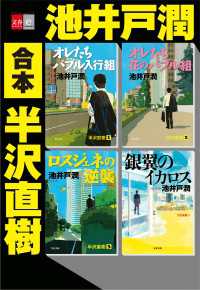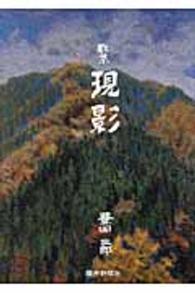- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
古代人との魂のひびきあいを生涯にわたり、悲劇的なまでに求め続けた人・折口信夫。日本各地への旅のなかで発見された「まれびと」、短歌創作を通した教育、新しい国学の提唱、そして敗戦後の日本において育もうとした人類教的な神……。現実との葛藤を常に抱えながら展開された折口の学問とはいったい何であったのか。最後の弟子が足跡のひとつひとつを確かめながら、折口の内面の真実をつぶさに描き出す。師への追慕と鎮魂の念に溢れた傑作伝記。第14回和辻哲郎文化賞受賞。
目次
一 古代学と万葉集
二 万葉学とアララギ
三 まれびと論以前
四 力ある感染教育
五 内なる「まれびと」論
六 国学と神道
七 国学の伝統
八 「まれびと」とすさのを
九 日本人の神
十 時代と批評精神
十一 新しい神の発見
十二 折口の古代と出雲
十三 折口のブラック・ホール
十四 慨みの声としての短歌
十五 古代への溯源
十六 時代と学問
十七 敗戦による、死と再生
十八 二つの『死者の書』
十九 『死者の書』の主題
二十 敗戦の後の思想(一)
二十一 敗戦の後の思想(二)
二十二 神道の宗教化(一)
二十三 神道の宗教化(二)
二十四 日本人の他界観
あとがき
文庫版あとがき
作品・論文名索引
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
フリウリ
4
なかなか難しくて読み込めないでいる。その理由の1つとして、岡野氏の折口信夫へのおもいの深さが「言葉をこえている」ことがあると思うのだが、他方、折口の感情の起伏、「おほやけばら」(公腹=時代に対する大きな怒り)と短歌・詩との関係、「まれびと」としての神と「みこともち」としての神(=天皇)とか、示唆を得ることは多い。最近、岡野氏による「源氏全講会」がyoutubeで公開されているのを知った(森永エンゼルカレッジ)。三矢重松、折口を継ぐ「全講会」と並行して本書を読むと、別の糸口がつかめそうな気がする。72023/02/28
はるぴょん(ひらた)
2
著者は折口の弟子として、その晩年に起居を共にした歌人。歌の解釈を中心にしながら実際に見聞きしたエピソードも交えつつ、折口の胸の秘奥を丹念に描いているという印象。伝記はともすると無味乾燥に陥りがちだが、本作はそうではない。個人的に惜しいと思ったのは民俗学に関する叙述が少なかった点。マレビトや霊魂観などの中心概念には触れられているものの、それ以外の民俗学に関する話題が少なく、やや物足りない感じがした。2020/02/25