- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
目黒女児虐待死事件で、5歳の被害児は保育園にも幼稚園にも通っていなかった。このような「無園児」家庭に、虐待、貧困、発達障害などの問題があっても、その実態は表面化しづらい。日本全国に3歳から6歳児で9.5万人いると言われている無園児の実態と就園の障壁について、全国4万人を対象とした研究の成果と、無園児の家庭や支援団体への取材を紹介する。病児保育のNPO法人フローレンス代表、駒崎弘樹氏との「幼児教育義務化」についての対談も収録。
目次
はじめに なぜ、「無園児」が問題になるのか
「目黒女児虐待事件」に見る、無園児という問題
無園児問題との出会い
待機児童問題を通じて痛感した子育て支援不足
社会で子育てする文化が醸成していない
なぜ本を書くことにしたのか
本書の構成
第一章 「無園児」は、さまざまな問題を解く鍵になる
(1)どのような子どもが無園児なのか
日本では九・五万人が無園児と推計
幼児教育の多様な選択肢
保護者による幼児教育の選択
全国四万人を対象とした研究
なぜ無園児になりやすいのか
他の先進国での無園児の状況
(2)貧困家庭に育つことの将来にわたる不利
貧困とは
貧困は子どもの「今」と「将来」を脅かす
乳幼児期の「貧困」が最も有害
「貧困」が乳幼児の発達にもたらす二つのプロセス
(3)貧困の連鎖を断つ鍵となる幼児教育
ペリー就学前プロジェクト
社会的に不利な家庭の子どもにこそ効果がある
子育てストレス軽減による子どもの発達状況の改善
セーフティネットとしての幼児教育施設
第二章 「無園児」家庭の実態──取材を通して見えてきたこと
(1)当事者への取材から
発達の遅れを指摘され、保育園に入れなかったブラジル人の女の子
発達障害グレーゾーンで入園を断られた男の子
医療的ケア児が、保育園にも児童発達支援施設にも入れない理由
(2)支援団体への取材から
認定NPO法人PIECES代表理事 小澤いぶきさんに聞く
公益財団法人かながわ国際交流財団 多言語支援センターかながわ総括 富本潤子さんに聞く
NPO法人K 理事長 Oさんに聞く
第三章 周りができることは何か──国の政策、地方行政、地域の支援
(1)幼児教育・保育の無償化議論に子どもの目線を
無償化は誰のため?
機会の公平性の実現を
〇~二歳児に対する保育の必要性
(2)取り残された子どもたちを幼児教育につなぐ
無園児を把握する
無園児を幼児教育につなぐ
妊娠期からの切れ目ない支援
(3)障壁を取り除く①──申請のハードルを下げる
(4)障壁を取り除く②──多様な言語や文化への対応
増加する、海外にルーツを持つ子どもたち
就学の実態
幼児教育につなぐために
(5)障壁を取り除く③──障害のある子どもや医療的ケアの必要な子どもへの対応
障害のある子どもや医療的ケアの必要な子どもとは
障害児保育と児童発達支援
支援の地域格差
幼児教育につなぐために
(6)インクルーシブな社会へ
特別対談 幼児教育「義務化」がなぜ必要なのか? 駒崎弘樹×可知悠子
1 義務化の意義は何か
最も厳しい環境にいる子どもたちこそ幼児教育が必要
なぜ無償化では不十分なのか
フランスは義務教育を三歳からに引き下げ
2 義務化と言っても、毎日行かなくていい
本質的な意義は地域社会とつながること
幼児教育では遊びが重要
3 義務化へのハードルとは何か
待機児童問題
家庭で子どもを教育する自由
保育の質の評価
幼児教育施設の多様性
おわりに
【引用文献】【参考文献】
第一章
第三章
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
ねこけし
Schuhschnabel
ネギっ子gen
コピスス
-
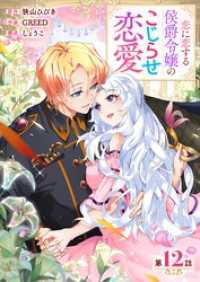
- 電子書籍
- 【分冊版】 恋に恋する侯爵令嬢のこじら…
-
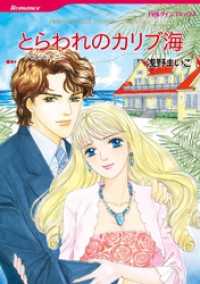
- 電子書籍
- とらわれのカリブ海【分冊】 4巻 ハー…
-
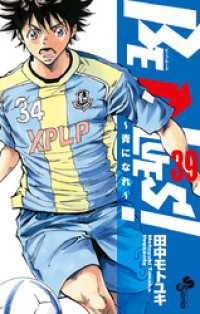
- 電子書籍
- BE BLUES!~青になれ~(39)…
-

- 電子書籍
- メイドと吸血鬼 28 NETCOMICS
-
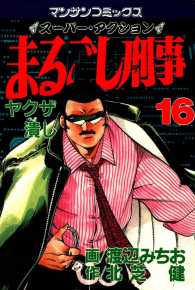
- 電子書籍
- まるごし刑事 - 16巻




