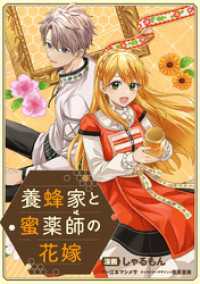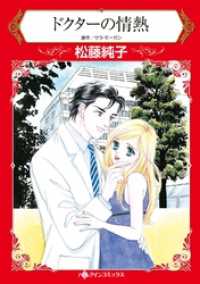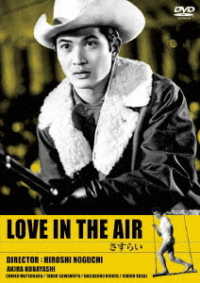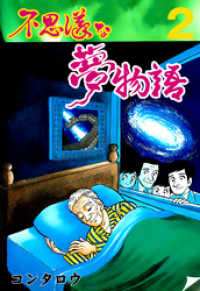- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本古代の宮室・都城の発掘調査は昨今急速に進み、研究も活況を呈している。そこで、古代の代表的宮都を、飛鳥の宮々・難波宮・大津宮から藤原京・平城京・恭仁京・紫香楽宮・平安京、さらには大宰府、平泉に至るまで十五講にわたって紹介。最新の調査成果と、深まりゆく研究を紹介しつつ、宮都の実像を叙述するだけでなく、各時代の社会的背景となる古代都市のあり方をも明らかにする。一般読者に向けて先端研究を解説し、旧来の古代史イメージを刷新するシリーズ第三弾。
目次
1 飛鳥の宮々 鶴見泰寿
2 難波宮 磐下徹
3 大津宮 古市晃
4 藤原京 市大樹
5 平城宮 山本祥隆
6 平城京 佐藤信
7 恭仁京 増渕徹
8 紫香楽宮 北村安裕
9 長岡京 國下多美樹
10 平安宮 北康宏
11 平安京 西山良平
12 白河・鳥羽 土橋誠
13 大宰府 杉原敏之
14 多賀城 古川一明
15 平泉 佐藤嘉広
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
terve
31
佐藤先生編の第三弾(第一弾、第二段は未読)です。今度は宮都編ということで、日本の宮都について各論が出されています。個人的には難波宮や紫香楽宮、恭仁京が興味深いですね。特に難波宮などは、山根徳太郎という碩学がいなければ発見すらされなかったであろうことは知るべきでしょう。時代背景にも依りますが、発達と歴史を天秤にかけ、歴史が取られる今の世の中に有り難さを感じます。過去には、発展のために消し去られた遺跡もあるのでしょう。2020/03/21
chang_ume
13
考古学の知見を中心に、「古代都市」の具体的様相が紹介される。畿内では、聖武天皇の迷走と解されてきた平城京から恭仁京・難波京・紫香楽宮への宮都の移動について、副都制の導入さらに大仏建立という、聖武の明確な指針を想定した解釈が示される。一方で、畿内を離れた九州(太宰府)と東北(多賀城・平泉)についても、方角地割を含んだ都市的要素があきらかで、共通性と地域性の双方からこれらをどう取り扱うか。桓武期の山城遷都(ひな壇状造成の長岡京、都市域が変遷する平安京)の実態とあわせて、理解の現状到達点となるような一冊です。2020/03/23
アメヲトコ
10
20年3月刊、古代史講義シリーズの第3冊。飛鳥から平安京までの古代の都と、大宰府・多賀城・平泉といった地方拠点まで、主要な15の宮都について解説しています。発掘調査の進展で続々と復元案が変わる古代都市だけに、最新の研究成果がコンパクトにまとめられているのはありがたいです。平城京の「十条」大路についてはふれられていないですが、まだ書くまでにはということでしょうか。全体を通してみると平泉はかなり異質な都市構成で、古代宮都の系譜というよりは中世都市という印象です。2020/03/29
はちめ
9
各宮都とも大まかな想定図が掲載されており、恭仁京、紫香楽宮、長岡京などそれぞれ本格的な宮都を造ろうとしたということは分かる。それにしても、天武天皇や聖武天皇はなぜ遷都を繰り返したのか。建築資材は旧都からの使い回しが多かったようだが、それにしても国及び人民の負担は大きかったと思う。住民や諸国の負担を増やして疲弊させること自体が目的だったというのはどうだろうか。裁兵の発想で。☆☆☆★2020/04/27
眉毛ごもら
5
飛鳥時代から平安京に至るまでの各宮都と、鳥羽白河離宮、太宰府、多賀城、平泉と主要大都市についての最新研究の概説。発掘作業の進歩ってすげーとなるのである。数年の都も千年の都も考えて作って行ったのだと言うことが発掘作業でわかったときは、テンション上がるだろなーと思う。聖武帝のご乱行だと思ってた紫香楽宮と、恭仁宮も意外と考えて作られてたのはびっくりした。メンヘラ金持ちのご乱行だと思ってたから。リアル三都物語壮大ですわ。壮大すぎてポシャったけど。太宰府は去年行って歩いてきたので一番わかりやすかった。実地大事。2020/04/05