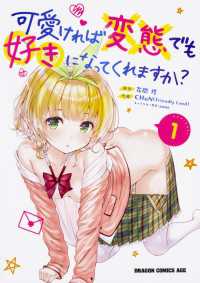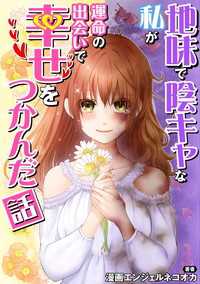内容説明
建築史家であり、複合施設「ラ コリーナ近江八幡」や「多治見市モザイクタイルミュージアム」など斬新な施設を生み出す建築家として話題の著者が語る半生と、独自の建築・文明観。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
6
郷里の大先輩、藤森照信先生の自伝エッセイ。知ってる地名や、子どもの頃の遊びの風景など、懐かしさに溢れていて、ページをめくるのがもどかしいほどにさっと読み切ってしまう。先生の著作はあまり見かけないなと思っていたらどうして、百冊になんなんとする量作家でびっくり。そういう意味では、本書は奥深い藤森ワールドへの最適な入門書ではないかと思う。先生が初めて設計、建築をした「神長官守矢史料館」では、訪問を重ねる度に、信州諏訪という地にこれ程相応しい建物もないのではとの想いを深めている。・・・訪問するのは春以降がお薦め。2020/02/26
カエル子
5
著者が設計した小泊Fujiにて借り読み。最後の略歴まで面白い。4歳で「工夫してものをつくる楽しさに目覚め、6歳で上野動物園の園長に憧れた少年が、自分の人生をふり返る自伝的な著作。生まれ育った環境から学べることをすべて学び、問い続けた結果として成した建築の数々。無意識の器としての住宅と意識の器としての建築。これまであまり考えたことのないことを突きつけられて思いがけない良い読書となりました。ちなみに、宿自体は、環境も含めた箱としては素晴らしかったけど、家具や照明などの細部はイマイチだったというのが本音。2025/05/02
niki
1
この方の建築は存じていたが、お顔や経歴は存じ上げず。勉強になりました。 内田祥三という人が大正8年に決めた法律で、防火のために外に木を出してはいけないとした。そして都会から木が消えた。内田は晩年、街を歩きながら「間違ったかなぁ」と言ったらしい。この法律が違うものであれば、外壁に木がある美しい街並みが存在したのだろうか。2023/03/17
おさや
1
住宅は無意識でありたいからハウスメーカーが多い 言葉と作ることの和は一定 2021/07/29
みほた
1
藤森さんが建築や自然に対してどのように関わってきたのかを知れた一冊。藤森さんが言う記憶の器が印象深い。本人の建築を実際に生で見たとき、人間にある根本的な、信仰的な何か言葉にならないパワーを感じた。あの瞬間に感じた記憶を自分なりに解釈して建築と向き合いたいなと思う今日この頃。2020/12/26