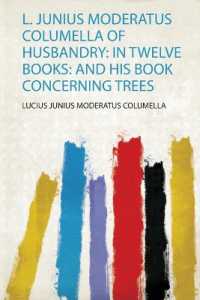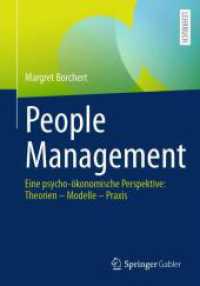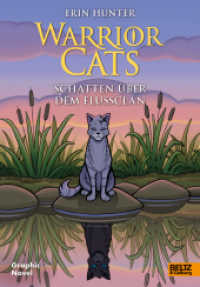- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
「考え方」がわかれば、だいたいの問題は解決する!
――『ストーリーとしての競争戦略』著者
一橋大学大学院教授 楠木建 絶賛!
商品「哲学」。
職種「哲学者」。
著者は日本で初めて「哲学専門の会社」をスタートさせ、
独自の「哲学コンサルティング」を実施している哲学者。
「哲学が、どうビジネスで使えるのか? 」
という疑問に真っ向から挑み、
組織においても、個人においても現状を変えていく突破口を見つけ、
圧倒的な成果とインパクトをもたらしています。
その思考のメソッド「哲学シンキング」は、
リクルート、ライオン、東芝、横河電機など、
錚々たるトップ企業がこぞって採用を決め、
いまや著者のコンサルティングは行列が必至です。
とはいえ、よく寄せられる疑問は、たとえばこんなことでしょう。
★哲学って難解なんじゃないの?
★「教養」の肥やしにはなっても、仕事の役には立たないのでは?
★覚えなくてはいけないことがたくさんありそう
いいえ、必要なのは、A4の紙とペン1本だけ。
実際に企業ではこんな課題に応え、驚くべき成果を上げています。
★現状の何が課題で、どこから解決の糸口をつかめばいいか? (課題発見→問題解決)
★「創造的なプロダクト」「刺さるサービス」とは? (マーケティング)
★変化を起こす「斬新な提案」とはどこから出てくるのか? (アイデア創出)
★組織のモチベーションを上げるにはどうすればいい? (コーチング)
★「持続可能な目標設定」はどこに定めればいいか? (ビジョン構築)
★みんなが働きやすい職場とは何か? どうつくればいいのか? (環境改善)
今後5年10年のビジネスは
「問題解決型」の能力より、
「課題発見型」の能力が重視される時代。
従来のビジネススクールで重宝された問題解決のフレームワークでは、
「クリエイティブで美しいイノベーション」を起こせるのかどうか
――そんな声も聞かれます。
そんななか「グーグル」「アップル」といった世界的な大企業が
つぎつぎと「社内哲学者」の採用を決め、
哲学的思考力をビジネスに取り入れる潮流が生まれてきました。
本書の「哲学シンキング」によって「次の課題を見極める力」を高めることは、
世界のトップ人材に求められる「新時代型の能力」を身につけることに他なりません。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えんど
sho watabe
Bartleby
めかぶおじさん
しゅー