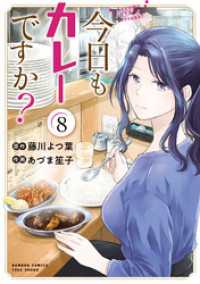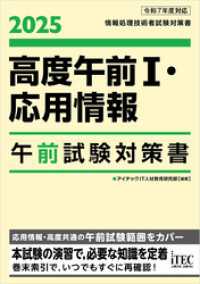- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
戦争で親を失い路上生活を強いられ、「駅の子」「浮浪児」などと呼ばれた戦争孤児。飢えと寒さ。物乞いや盗み。戦争が終わってから始まった闘いの日々。しかし、国も周囲の大人たちも彼らを放置し、やがては彼らを蔑み、排除するようになっていった。「過去を知られたら差別される」「思い出したくない」と口を閉ざしてきた「駅の子」たちが、80歳を過ぎて、初めてその体験を語り始めた。「二度と戦争を起こしてほしくない」という思いを託して――戦後史の空白に迫り大きな反響を呼んだNHKスペシャル、待望の書籍化。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
215
たった1枚の写真が、この本を生んだ(帯にも印刷)。京都駅前の「駅の子」と題された、戦争で親を失った戦争孤児、と思われる写真だ。破れた帽子をかぶって身なりは貧しそうだが、はにかむような笑顔で目には生きようとする力が漲っている。こんな子たちの真実を「もっと知りたい」と、かつての「駅の子」たちへの直接取材が始まった、という。孤児の中には「思い出したくない」記憶も多く、聞き取りは困難を極めた。中には、アメリカに渡って米国籍を取得し「日米の架け橋」になった人も。これまで”空白”だった戦後の貴重な記録が読めた。2020/03/25
へくとぱすかる
80
戦争が終わって、親を亡くした子どもが直面したのは、悲惨な生活だった。飢えや凍死、病気で死んでしまった孤児も多数いた。その実態について、政府も多数の市民も、ほとんど正確な人数すら調査せず、放置か厄介者として扱った。集団でおりに入れるなど、虐待そのものではないか。高齢になった今、証言できる人も少数で、過去を言えない、思い出したくない人も多い。70年以上過ぎても、当時を思い出すと号泣するほど心の傷は深く、世間はいつも弱い立場の人間に冷たい。この本は、まだ何の補償も行われていない現代史の谷間を告発している。2020/03/16
天の川
42
古内さんの「鐘を鳴らす子供たち」の戦災孤児光彦の悲痛な叫びに胸を突かれて手に取った。Nスペの取材記録。一日にして親の庇護を失った子供たちの苦難がどれほどのものだったか、社会からの差別がどれほどひどいものだったか、取材に応じてくれる人の少なさが物語る。「みんな飢えていた。食べ物もなく、着るものもなく。でも何より飢えていたのは温もりだった。」親に手を引かれる子どもを見て、石を投げた…そんな子どもが12万人もいたこと、彼らの存在に目を背けるばかりか、犯罪予備軍と見なす社会だったこと、決して忘れてはいけない。2020/04/14
ころこ
40
以前、愛着障害の本で戦争孤児が取り上げられていて、印象に残っていた。ぼくが想起したのは『火垂るの墓』ではなく、『この世界の片隅に』で、最後に拾われた戦災孤児は単なるハッピーエンドではなく、愛着障害にはることはないのか、というものだ。著者はNHKの番組制作者で、同名でNスぺを制作している。この機会に、同番組も観た。証言者の方が戦災孤児を代表しているのではなく、象徴性が壊れた世界が出現して徒手空拳でその中を生きていく、ただそのひとの経験としてこそ読む意味がある。辛く当たった親戚の立場になると、敗戦による価値の2023/02/20
たまきら
37
上野育ちの90歳になる隣人が、「駅の子たちは悪くてねえ…」と戦争体験をうかがっていた時言っていたけれど、その「駅の子」という言葉がかなり一般に使われていた言葉だとは思ってもいませんでした。前回のNHK朝のドラマで、娘が戦災孤児について初めて興味を持ちました。以前お会いした鎌田十六さん(戦災孤児を育てた孤児院に勤務していたおばあちゃんです)からもうかがっていましたが…。東京以外の様々な駅でも…。あの頃の子供たちの記録を読みながら、弱者にとっての戦争がどういうものか、かみしめました。読み友さんから。2020/12/22