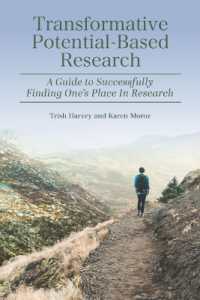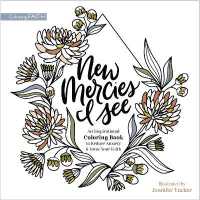- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
足利一門大名に丸投げして創立された室町幕府では、南北朝の分断などに後押しされて一門大名の自立心が強すぎ、将軍の権力が確立できなかった。この事態を打開するために、奇策に打って出たのが足利義満である。彼は朝廷儀礼の奥義を極め、恫喝とジョークを駆使して朝廷を支配し、さらには天皇までも翻弄する。朝廷と幕府両方の頂点に立つ「室町殿」という新たな地位を生み出し、中世最大の実権を握った。しかし、常軌を逸した彼の構想は本人の死により道半ばとなり、息子たちが違う形で完成させてゆく。室町幕府の誕生から義満没後の室町殿の完成形までを見通して、足利氏最盛期の核心を描き出す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南北
62
足利義満を「朝廷と幕府を一身に支配する、日本初の統一的支配者」という観点から論じた本。足利尊氏から義教の時代までをみることで義満の特異な部分が見えてくる。かつては皇位を奪おうとしていたとされていた義満だが、現在は否定されている。命令するのではなく、「してくれたら嬉しい」といって家臣や公家たちを従わせるのは恐るべきパワハラと言えるだろう。新説もいくつか提示されていて、とても興味深く読めた。2021/05/07
kokada_jnet
51
読むのが遅れましたが、2020年刊のベスト本かも。ジョークまじりのパワハラで、公家や皇族たちをガンガンと追い詰めていく足利義満のキャラクターが、生々しく、また、ヒジョーに恐ろしいけれど面白い。一級のホラーストーリーで不条理劇。この著者の本は、どれもあたりで、はずれがない。「他の研究者の本には、一度もでてこない」として紹介される、発掘もののエピソードが多いのも、この本がふつうの新書レベルを超えているところ。2021/04/17
ぽんすけ
29
改めて室町幕府の特殊性と足利義満の特異性について考えさせられた。誰もが一度は見たことがある金閣寺、学校では北山文化の中心的存在として習うけど、そもそも北山文化とは「北山(だけで十年間義満だけが楽しんだ超ローカル)文化(というより個人の趣味)」だったことが驚愕である。第一層が公家寝殿造、第二層が武家書院造、第三層が禅宗様と各層様式が違うエキセントリックな作りからもそれが伺える。又彼は幻想の世界を極めて新しい世界を作った観阿弥世阿弥の最大のパトロンであり、この北山で壮大な非現実的空間を作りあげそれに浸り、尚且2024/12/21
鯖
27
タイトルは義満だけど、六代義教までの各将軍を追った本。直義から始まり、兄弟相克の状態がひたすら続く室町幕府。確かに永享の乱の遠因も直義ではあるんだよなあ…。北山文化は義満1人の個人的趣味で、HN(日本国王臣源)で呼び合い、唐を模した虚構を愉しむ義満の姿という指摘にはなるほどなーと。自らを光源氏になぞらえた(寵妃との密通疑惑等)ことも例示されてたけど、他にもひすちょりあで見た大江山の鬼退治は義満の日明貿易での業績(鬼=倭寇)というのも一緒で、人身極めすぎて虚構で遊んでたのかな。面白かったです。再読したい。2021/05/09
ロビン
26
日本史上初めて征夷大将軍と太政大臣を兼務し、南北朝を統一し、史上誰よりも天皇に近づいた男・足利義満を中心に、足利尊氏・直義の争いである観応の擾乱から、義満の息子義嗣、義持、義持の弟で第五代の義教までを、後円融天皇や後花園天皇など朝廷や天皇たちと絡めながら描いた新書。義満が朝廷に食い込んで公家たちの生殺与奪を握って君臨し、北朝を代表する存在となって南朝と交渉して初めて南北統一がなされた、との解説に感嘆した。義満は独創的でやり手だが、あまりにジャイアンなので大河ドラマの主人公にはなれなさそうだなあと思った。2022/06/04
-

- 電子書籍
- 薬売りの聖女【分冊版】 18 FLOS…
-

- 電子書籍
- 鍛えてマスター電気数学 -計算問題を制…