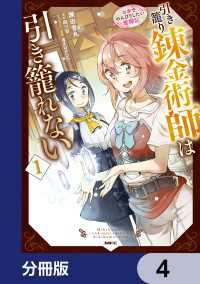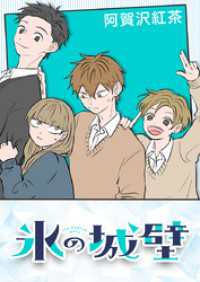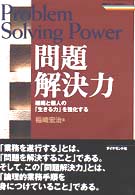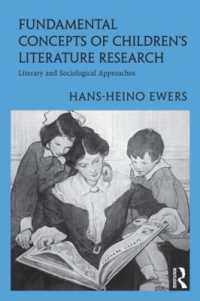内容説明
シリコンバレーで起業した30代後半、日系3世の女性レイ。
80年代アメリカの小学校時代に周囲から受けた壮絶ないじめの後遺症を今も抱えながら、黒人の同僚とコンビで自社製品のプレゼンに駆り出される日々を送る。
精神安定剤を手放せないレイは、大仕事を前に休暇を命じられ、旅に出る。
日系1世の祖父母が戦中に入れられたマンザナー強制収容所、レイの母がひとり暮らすリトル・トーキョー。自らのルーツを歩いたレイは、目を背けていた本心・苦しみの源泉を知った。
複雑な形で差別の問題が日常にある3世の苦しみ、母親との関係。
日本とは、日本人とは、私とは何か――。
VRや音楽のミキシングアプリを対比させ、問題を鮮やかに巧みに
浮かび上がらせる。「マイノリティとしての私たちのこと」を問いかけた傑作。
第30回三島賞受賞。芥川賞候補。
「一読者として非常に感銘を受けた」平野啓一郎(選考委員)
様々な人種が暮らし、薬物の誘惑も幼児虐待も当たり前に転がるニューヨークで、女子プロレスラーとして働く姉の稼ぎで小学校時代を送った。やがて当たり前のように、一つの悲劇が起こる――日本人青年が、かつての生活を振り返る「半地下」も収録。
解説・鴻巣友季子
※この電子書籍は2017年1月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
南雲吾朗
65
表題作「カブールの園」。アメリカ移民1世と2世の民族意識の隔絶。母国語、風土の違いによる意識・伝達の違い、感じ方の違い。人種差別。アイデンティティーの乖離。それらの間で揺れる人間像。そんな中でも、アメリカ人として生きていこうと必死になる姿が痛ましい。物語りの中に出てくる風土・言語の考え方・捉え方が、私にっとって、すごく納得がいった。「言語の持つ抒情の体系は、風土が変わっても容易に変貌しようとはしない。」以前から、自分で感じていた事をこうも的確に言葉にされては…。(続く)2020/04/18
路地
52
職業柄、職場に多い帰国子女や日系人が抱えているかもしれないアイデンティティに対する疑問や苦悩を垣間見る読書体験だった。実際に住んだこともない自分には知り得ない(知ろうとしてこなかった)差別の実態と、それが間接的に親子関係にも影を落とすことになる様子に胸が苦しくなるが、折り合いをつけて生きる様子に強さも感じる。2023/01/30
miri
38
第30回三島由紀夫賞受賞作。アメリカに住む日系三世のアイデンティティの問題をテーマにPTSDやドラッグ、人種、言語問題を絡める。後半の『半地下』の物語の方がより叙情的な表現。幼い頃の時系列に沿わない記憶の連なりがそう感じさせるのか、ドラッグの高揚と鬱がそう思わせるのか、現実の重さは感じない。他は何であれ、自分が日本人であるということには帰属意識があるので、所在なさを想像するのが難しかった。この所在なさを提起して、そののち、何を読者に考えさせたかったのだろう。そこが気になる。2025/02/11
hanchyan@発想は間違ってない
35
表題作は、自分を見失いそうになった主人公が改めて己のルーツに目を向け、自己を見つめ直すはなし。併録作は、正に懊悩の最中にいる主人公が己の半生を振り返るはなし。共通するのは、自分が今ここに有るのと同様に歴史が有る、という再認識だ、今ここに自分が有るためには自分を産んだ親が必要であり、ジーちゃんバーちゃんにも親がいて、さらに……と。当たり前のことではある。けども、我々は各々のルーツについて立ち止まって考えることは希だ。何よりも速度に価値を置き停滞を許さない社会に生きてるから。だこらこそ、この物語が刺さる。2021/03/27
hnzwd
25
人種、文化、ドラッグ等々について考えさせられる中編二作。SFの印象が強かった宮内さんですが、、ゴリゴリの社会派。子供時代に受けたイジメと、実母とのギャップでのPTSDとか、色々、考えさせられます。2020/04/26