内容説明
織田信長は戦国大名の中で唯一、天下をほぼ手中にした存在です。それと同時に「楽市楽座の開設」「比叡山など寺社に対する攻撃」など非常に変わった施策をしています。本書は、元国税調査官の著者が信長の生涯をこれまでとは違った「お金」「経済」という視点から読み解く、まったく新しい歴史読み物です。官職を蹴って金融改革に乗り出し、大減税で脅威の2500%経済成長を達成した経済の覇王・信長があなたの歴史観を変えます!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
53
とても面白かった😆著者は、元国税調査官で、現在ビジネス関連を中心としたフリーライターの大村大次郎氏。著者の経歴らしく、織田信長の生涯を「お金」「経済」の流れで読み解いていこうという趣旨の異色の歴史考察本。巷に溢れる歴史的な戦いや武将列伝をメインとする歴史本とは全く違う観点からのアプローチでとても興味津々でした。領地より港を優先して実利を得ること、既得利権を廃して競争市場を導入したこと、官職を蹴って金融改革に乗り出したことなど、「経済の覇王」としての信長が垣間見れます。2025/05/21
sayan
24
実務家が自身の専門性とフィールドに引き付けて歴史を語る。大半は強引なロジックと解釈に食傷気味になるが、時に「お!」となる発見もある。本書を手に取った際は、まあ、そういう期待値であった。ところが、個人的には「お!」となる発見が多く刺激的だった。特に「天下統一」を目指し裏付けある行動をとったのは?と疑問を置き、各武将分析過程から見える(個人的には)新たな意味合いは非常に興味深かった。時代時代で目指す方向はあるけれど「人・もの・金・情報」の流れに影響する動きがその時代を作ることは変わらないな、と改めて認識した。2020/02/15
こも 旧柏バカ一代
22
経済感覚が希薄な戦国時代と思ってたが、応仁の乱からして銭が原因だったとは、、世の中が不安定になり、利権も乱立して税を支払う民は困窮していき世の中は殺伐として来た。それを解決するように勢力圏を伸ばしたのが織田信長が率いいる織田家だった。織田信長は、寺院や土着の国人達から徴税権を統一し、経済が発展するように関をの徴税を撤廃。あれ?関が消費税みたいに見えたぞ?そうして税金を織田家以外が勝手に取られないように整理して統治していたが、価値観の合わなかった新参者の明智光秀に討たれてしまったらしい。あぁ、、残念。2024/10/20
ウラー
5
信長領は税が軽かった。また従来一般的だった金納でなく物納を認めた。農民の不満は減り、領内の一揆が抑えられたため、常に軍隊を外縁部に配置することができ、急速な領地拡大を可能とした。/港を支配し、商人から税収を得ていた。その金で常備軍を組織した。常備軍だったからこそ、頻繁に居城を替えることができ、常に前線近くに根拠地を置くことができた。家臣が兵農分離できていない他の大名は、家臣の領地から離れたところに居城を替えることはできなかった。/戦国時代は天下取りレースではなかった。信長だけがその意志を持っていた。2020/03/09
neatANDtidy
3
昔の比叡山の嫌われぶりが大胆に書かれていた。2022/04/15
-
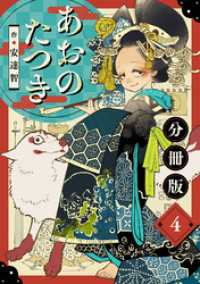
- 電子書籍
- あおのたつき【分冊版】4
-
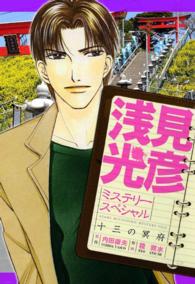
- 電子書籍
- 浅見光彦ミステリースペシャル 十三の冥…





