内容説明
GDP世界二位の中国と、三位の日本の関係は、米中関係に次いで世界で二番目に重要な二国間関係だと言える。だが、日中関係は「緊迫」「危険」「難解」「複雑」という言葉が当てはまる。尖閣諸島周辺では、いまなお両国が日常的に対峙し、危険な衝突が起きる可能性が高い。もし二国間関係の取り扱いを間違えば、両国は軍拡競争に走り、二国間、地域、グローバルな問題での協力は行き詰まり、最終的には紛争になるだろう。
だが、日中関係を適切に取り扱うことができれば、両国は国際秩序と地域の協力枠組みを守るために協力し合える。貿易、経済建設、研究開発、平和維持、自然災害対応などの分野で、両国は力を合わせていけるはずなのである。
日中の指導者たちは、両国関係を発展させていくには、相手国が歴史に対して真摯に向き合うべきだと発言している。日中関係は1500年にわたる長い歴史を持ち、両国国民は過去の歴史に対する深く複雑な感情を有している。そのため、両国の研究者が集まって歴史観をすり合わせようとしても、新たな緊張関係を生みだし、重要な問題についてはほとんど合意が得られない。
しかし、両国の協力関係と友好関係のためには、歴史問題の超克は不可避の課題だ。本書は、日中両国の研究者であるエズラ・ヴォーゲルが、7世紀の遣隋使以来の1500年間におよぶ日中関係を網羅し、第三国人の視点から客観的な日中関係史を提供するものである。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
16
日本が中国に学んだ時代、中国が日本に学んだ時代、抗日の時代、再び中国が日本に学んだ時代、そして日中関係が悪化した現在という構成。中立性は意識されているようだが、やや日本側を贔屓しているというか、日本側の見解に拠っているかなという印象。近代の部分では、「シナ通」の活動や功罪について1節分程度割いても良かったのではないかと思う。中国の抗日ドラマについて触れている部分もあるが、このジャンルが映画において抗日戦争当時から存在していたことを失念しているのではないか。2020/03/06
Hatann
10
日本及び中国について研究する米国の社会学者が第三者的に日中関係の歴史を素描する。1500年の歴史を纏めるものだが、19世紀以降が圧倒的に詳細に記載される。全体的に一方に肩入れすることなくバランスの良い記載だと思う。日清戦争直後や改革開放路線直後に中国側で日本に学ぶことがブームになるが、こういうモメンタムを活かせなかったところを良く考えてみるべきだろう。著名人の活動にも焦点をあて功罪を記しているが、満州事変以降について日本側の個人名がほぼ記されないことが気になった。知恵といえば知恵。全体的には読み応えあり。2020/01/05
sakadonohito
9
有史から2017年までの日中の関係史をできるだけ中立視点で書いたもの。明までは日本との行き来は寧波だったようだ。明治時代は西洋に追いつけとたくさん海外留学して国際感覚や人脈を気づいた人達が政治をリードしていたこともあり良かったが、だんだん調子に乗ってきて国際関係に疎く国粋主義的な風潮が高まるに連れおかしくなっていった。戦後については、江沢民政権から反日教育とプロパガンダが急激に増えてる。日本のGDPを抜いた2010年から対日強硬路線。強い相手には弱く、弱い相手には強く。それが中国。2024/09/27
はまななゆみ
9
体系的に理解を深められました。先ずは歴史をニュートラルに、もっと勉強しなければならないでしょうね。両国ともに。2020/07/24
takao
3
ふむ2020/11/11
-
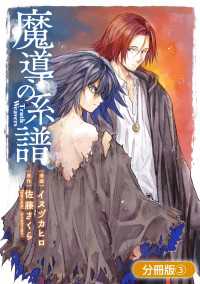
- 電子書籍
- 魔導の系譜【分冊版】(3) ブレイドコ…
-

- 電子書籍
- ビジネスで差がつく「自己アピール」の技…






