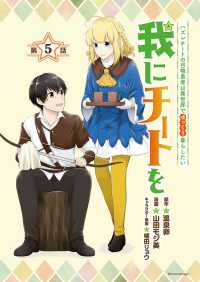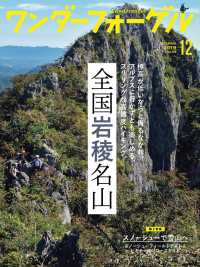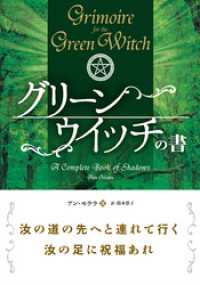内容説明
現存する最古の演劇といわれる、能楽。
今から約600年前の室町時代に、世阿弥(1363~1443?)は、当時の大衆芸能を芸術へと昇華させ、『井筒』『高砂』『砧』『実盛』『葵上』など今も上演される名作を遺し、『風姿花伝』を始めとする世界初の演劇論を執筆しました。
これほどまでの偉業をなしえたにもかかわらず、肖像画の1枚もない。
世阿弥とは、一体どんな人物だったのでしょうか? なぜこの時期に、これほどまでの仕事をなしえたのか――。
その時代背景や彼の思想哲学を、父・観阿弥や、禅竹、金剛などライバル達との作品比較、伝書から見る芸論などから細やかに考察。
晩年、大衆に拒絶され、自身も佐渡に流された世阿弥の生涯も辿りながら、彼が求めた「老いの美学」についても検証します。
本書は『世阿弥』(1972年 中公新書)より、舞台写真、資料写真を新たに差し替え、解説を加筆、文庫化したものです。
解説「異端者としての世阿弥」 土屋恵一郎(明治大学長)
目次
はじめに
第一章 世阿弥とその時代
一 猿楽能の誕生
寄合――観客層の拡大 物まね芸の系譜 歌舞の伝統
二 父・観阿弥
猿楽能と田楽能 天下の名望 「中初・上中・下後」の人
三 世阿弥の活躍――応永まで
生年論 同朋衆・時衆の問題 伊賀観世の系図 少年世阿弥 世阿弥と二条良基 将軍義満と世阿弥 世阿弥の再出発 北山邸行幸と義満の死 第一次苦境時代 寺社猿楽への後退 音阿弥の生長 応永末年の世阿弥
第二章 世阿弥の作品
一 能の作者
能の作者 世阿弥の作品 能の分類 世阿弥の作品傾向
二 大和猿楽の伝統――劇的現在能
大和猿楽の特質 観阿弥の代表作<自然居士> 観阿弥の作品傾向 群小作家の作風 大衆作家宮増 世阿弥と劇的能
三 能の神々――脇能
脇能と歌舞性 <高砂>と<竹生島> 神の影向 先行芸能延年風流 小風流と脇能 大風流と脇能 世阿弥の脇能 非世阿弥系作者の脇能 神は鬼がかり 世阿弥の脇能改革
四 『平家物語』と能――修羅物
修羅物と世阿弥 複式夢幻能 脇能と修羅物 古修羅の世界 花鳥風月と修羅 憑き物による物狂と修羅 “金剛”の作品 『平家物語』の二つの側面
五 王朝古典の世界――女体能をめぐって
王朝女性の能への登場 憑き物と女性 物狂から複式夢幻能へ――<松風> 物着と複式夢幻能――<井筒> その他の複式夢幻能――<融><須磨源氏>等 女体能の行方 <砧>の位置づけ――準夢幻能
第三章 世阿弥の芸論
一 世阿弥の伝書
世阿弥の伝書 伝書の時代区分 前後二区分説
二 『風姿花伝』
『風姿花伝』のあらまし 一、年来稽古 二、物学条々 三、問答条々 『花伝』四~六 別紙口伝
三 『花習』以後
『花習』以後の代表作 物まねから三体へ 花から幽玄へ 安定→蘭位→妙所
第四章 世阿弥の流れ
一 晩年の世阿弥
能役者としての世阿弥 第二次苦境時代 十二五郎の手紙 一座の危機 次男元能の出家 長男元雅の客死 「却来」という境地 佐渡配流 佐渡よりの書状 金春禅竹と鬼の能 最晩年
二 能の流れ
観世小次郎の活躍 キリシタン能と太閤能 世阿弥の影 能の固定化
世阿弥年譜
参考文献
あとがき
解説「異端者としての世阿弥」土屋恵一郎(明治大学長)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nishiyan
ちあき120809
全力背走