内容説明
『現代日本の精神構造』(1965年)や『近代日本の心情の歴史』(1967年)で日本と日本人がたどってきた道行きを具体的な事象を使って鮮やかに分析した社会学者は、人々を震撼させた連続射殺事件の犯人を扱う「まなざしの地獄」(1973年)でさらなる衝撃を与えた。その名を、見田宗介(1937年生)という。
続くメキシコ滞在を機に、さらなる飛躍を遂げた社会学者は、「真木悠介」の名を使ってエポックメイキングな著作『気流の鳴る音』(1977年)を完成させる。ここで形を得た人間観と、そこから導かれるコミューンへの憧憬は、独自の理論に結晶していき、数多くの信奉者と、数多くの優れた弟子を生み出した。その成果は、『時間の比較社会学』(1981年)や『自我の起原』(1993年)といった真木悠介名義による労作を経て、ついに『現代社会の理論』(1996年)に到達する。現代の世界に向けられた冷徹と愛情の共存するまなざしは、最新の社会現象についても常に鋭利な分析をもたらし、今なお他の追随を許すことがない。
その思想が、かけがえのない「他者」たちとの対話を源泉にして生まれてきたこともまた間違いのない事実である。対談や座談会は収録の対象としなかった『定本 見田宗介著作集』(全10巻、2011-12年)と『定本 真木悠介著作集』(全4巻、2012-13年)を補完するべく精選された、珠玉の11篇。現代日本社会学の頂点に君臨する著者が望んだ初の対話集がついに完成した。
[本書収録の対話]
河合隼雄 超高層のバベル
大岡昇平 戦後日本を振り返る
吉本隆明 根柢を問い続ける存在
石牟礼道子 前の世の眼。この生の海。
廣松 渉 現代社会の存立構造
黒井千次 日常の中の熱狂とニヒル
山田太一 母子関係と日本社会
三浦 展 若い世代の精神変容
藤原帰一 二一世紀世界の構図
津島佑子 人間はどこへゆくのか
加藤典洋 現代社会論/比較社会学を再照射する
交響空間――あとがきに(見田宗介)
目次
河合隼雄 超高層のバベル
大岡昇平 戦後日本を振り返る
吉本隆明 根柢を問い続ける存在
石牟礼道子 前の世の眼。この生の海。
廣松 渉 現代社会の存立構造
黒井千次 日常の中の熱狂とニヒル
山田太一 母子関係と日本社会
三浦 展 若い世代の精神変容
藤原帰一 二一世紀世界の構図
津島佑子 人間はどこへゆくのか
加藤典洋 現代社会論/比較社会学を再照射する
交響空間――あとがきに(見田宗介)
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
原玉幸子
かんがく
めん
ぷほは
マウンテンゴリラ
-
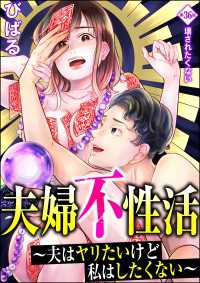
- 電子書籍
- 夫婦不性活 ~夫はヤリたいけど私はした…
-
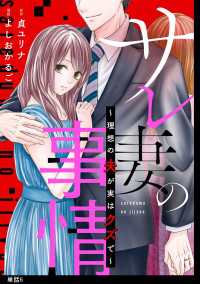
- 電子書籍
- サレ妻の事情~理想の夫が実はクズで~【…
-

- 電子書籍
- のだめカンタービレ 新装版(12)
-

- 電子書籍
- 峠鬼【分冊版】 6 HARTA COM…
-
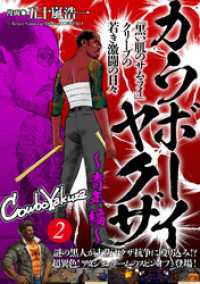
- 電子書籍
- カウボーイヤクザ~青年編~「黒い肌のサ…




