内容説明
文武兼ね備えたエリート武将は、いかに本能寺の変へと追い詰められていったのか。牢人医師としての出発点から、延暦寺焼き討ちで見せる冷酷さ、織田家中における異例のスピード出世、武官としての比類なき実力まで。近年急速に進む光秀研究の成果を踏まえ、謎多き素顔に英雄史観・陰謀論を排し、実証的に迫る。気鋭の中世史家による、渾身の一作!
序章 新時代の子供たち
第一部 明智光秀の原点
第一章 足利義昭の足軽衆となる
第二章 称念寺門前の牢人医師
第三章 行政官として頭角を現す
第四章 延暦寺焼き討ちと坂本城
第二部 文官から武官へ
第五章 織田家中における活躍
第六章 信長の推挙で惟任日向守へ
第七章 丹波攻めでの挫折
第八章 興福寺僧が見た光秀
第三部 謀反人への道
第十章 領国統治レースの実態
第十一章 本能寺の変へ
終章 明智光秀と豊臣秀吉
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
19
豊富とはいえない史料から、プロファイリングのように光秀の出自や家格、性格、口吻まで導き出しているのがおもしろい。最後に何が光秀と秀吉との運命を分けたのかという比較がなされているが、光秀はもうひとりの秀吉というか、秀吉になれなかった男として位置づければ、その歴史的価値が見えてくるのかもしれない。2019/11/14
浅香山三郎
18
今年の大河ドラマの主役・明智光秀について、新史料や近年の研究を元に、これまでとは違ふ人物像を提示しやうとする試み。医学の知識の豊富な浪人出身の武士、有能で多弁な文官、丹波攻めでの活躍、信長の側室・御妻木殿の存在など、確かに、余り注目されてこなかつた視角がうまく整理され、秀吉との比較検討を通じた中世と近世の統治スタイルの対比も興味深い。研究環境がよくなつた上に、後世に肥大化したイメージに依拠することなく、一次史料かそれに近いものを駆使してまとめる著者の伎倆が、新しい光秀像をより魅力的にしてゐる。2020/05/17
ようはん
18
急速に拡大していく織田政権に必要となる仕事をこなせる能力を光秀は持っていたという印象。だけど最後はガタがきててそれが本能寺の変の一要因になったとも言えなくもない。2020/02/07
nagoyan
15
優。著者は藤井譲治編『織豊期主要人物居所集成』に携わったことから光秀が「医師」だった可能性に気づく。この時期に医学が宗教から独立したということと、その医学に光秀が関わっていたということが、中世から近世への移行期の人格的表現者としての明智光秀像と確かによくなじむ。奈良の二大寺の係争の裁定にあたり百年以上前の文書は証拠能力がないと言い放つ辺りは中世から近世への移行期を思わせる。しかし、最後は、妹御妻木殿の死により信長との血縁を失った光秀は、信長の一族優遇政策から零れ落ち、身分の壁に再度阻まれる。2019/12/03
寝落ち6段
14
世は戦国。戦が頻発する中で、医学の重要性が高まる。明智光秀の詳らかになっていない半生を追っていく。どうやら医学に通じていたらしい。医学を基礎に、光秀の優秀さを詳らかにしていく。光秀の立場が、織田勢力の拡大によって変わっていく中で、激務と親族贔屓によって追い詰められたのかもしれない。信長への謀反は光秀だけではない。だが、光秀が有名になってしまったのは、ただ成功してしまったからなんだろうなと思う。2021/03/02
-

- 電子書籍
- 還暦から始まる 講談社+α新書
-
![[音声DL付]究極の英単語プレミアム Vol.1](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0874994.jpg)
- 電子書籍
- [音声DL付]究極の英単語プレミアム …
-
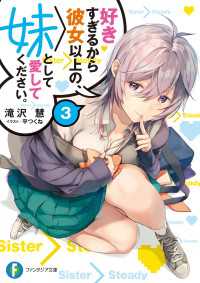
- 電子書籍
- 好きすぎるから彼女以上の、妹として愛し…
-

- 電子書籍
- First Stageシリーズ 電気・…
-
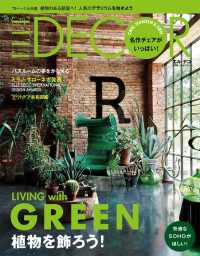
- 電子書籍
- ELLE DECOR - 2014年6…




