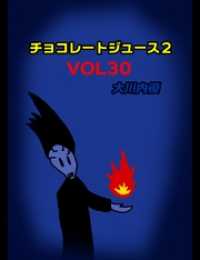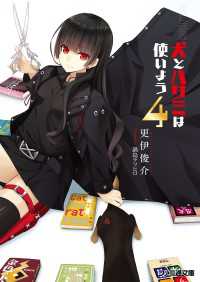- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
ノーベル経済学賞を受賞し、20世紀後半から21世紀初めにかけて世界に燦然たる輝きを放ったアメリカの経済学者ミルトン・フリードマン(1912―2006)。しかし、この「巨匠」がじつは繰り返し日本に関する分析と発言を行なってきたことを、どれほどの経済人が知っているだろうか。日本のバブル崩壊とデフレ不況を予見し、金融政策の誤りや貿易摩擦、構造問題を語った数々の言葉に、いまこそ私たちは耳を傾けるべきであろう。「私は日本の資本主義に誤りがあったとは思わない」。日本のエコノミストから「市場原理主義者」のレッテルを貼られた彼こそ、誰よりもわが国を救う「金融政策」および「減税」の重要性を論じていたのだ。「フリードマンの思想は誤解されがちだが、彼の分析は現代日本の様々な経済問題を解くための貴重な洞察に溢れている」(本書「はじめに」)。フリードマンの対日分析を、新鋭の経済学者が深く掘り起こした衝撃のデビュー作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てつのすけ
40
経済学者ということは知っていたのだが、どのような理論を主張されていたのか知らなかった。というより、経済学は、後付けでどのようなことでも言えるものだと思っていた。しかし、本書を読み、経済も、理論立てて考えることができることを初めて知った。バブル崩壊後、フリードマンの理論を採用していれば、我が国の経済は回復していたのではなかろうか?2020/05/18
健
11
かつてフリードマンは、所得が基礎控除額を下回るときは負の所得税を払う(=補助金を受け取る)ことができるという「負の所得税制」を提唱した。これは現在の給付付き税額控除制度とほぼ同じで、米国や英国等多くの先進国で実施されているそうだ。そんなの初耳なんだけど、そのような制度なら生活保護よりずっと良いんじゃないだろうか。新自由主義を提唱したフリードマンは貨幣の流通量を拡大させることが経済の発展に繋がると主張したようなんだけど、MMTとどこが違うんだろう。もっといろいろ読まないと。頭が混乱してきた。2020/03/11
Y田
11
フリードマンという人はこの本で初めて知った。金融政策と自由市場を重視する経済学者さんという認識でいいのかなと。金融政策と貨幣量に着目しての、戦後からの日本経済の解説が興味深かった。◉名目金利が下がっていても貨幣量が減るということもあるのか。てことは低金利でもデフレが続くのはあり得るのがわかる。◉インフレデフレを理解するのに貨幣的説明、非貨幣的説明という「違う立場」がある事を知ったが、これって理論ていうより「思想」みたいなもんなのかなと。だから緊縮増税派があれば逆にMMTとかがあったりする。そこに納得した。2019/12/26
佐藤一臣
10
金融緩和=公定歩合の引き下げだった昔、今は市中銀行の資産である莫大な国債を中央銀行が買う手法やマイナス金利といった手段が、フリードマンの実証研究の賜物だったというのがよくわかった。理由分析より、こうすればこうなったとの観察が重要なんだが、今の教育に観察教育は皆無だから政治家も官僚も観察力ないし、観察に割く時間もないんだろう。アベノミクスの金融緩和の効果はデフレの歯止めに絶大だったが、格差・貧困・福祉という弱い者の問題はまた別のやり方が必要で、減税や負の所得税や教育バウチャーを著者は必要と論じている2022/08/14
ベラ・ルゴシ
9
フリードマンが日本では過小評価、誤解されるのは何故か?「著者のような誤った解釈を喧伝するから」である。読んで更に嫌いなった。今時、金融緩和万能説はないだろう?「1998-2018oecd諸国の貨幣量と名目gdpの関係」と「OECD33か国の財政支出伸び率と経済成長。1997~2016」及び「日本のGDP/財政支出/マネタリーベースの推移」を比較すれば一目瞭然である。金融緩和だけでは効果は薄い、デフレには財政出動と金融緩和の量的緩和、車の両輪こそ効果的である。「財政再建には増税より、歳出削減」←ダメだこりゃ2020/03/22