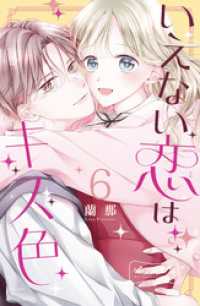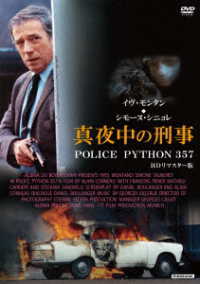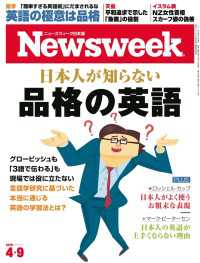内容説明
各地に残る「津」のつく地名は、かつて港に関連する土地だった。古代の船は喫水が浅かったので、港はラグーン(内海)に作られた。GIS(地理情報システム)を駆使して全国を探索し、土砂が堆積して陸化する前の景観を復元する。また港を支配し交易で栄えた豪族や、通商を担った海人(かいじん)族、港を繋ぐネットワークから、船・人・物の往来の実態を描き出す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
51
PCソフト「カシミール3D」を利用して、古代の海岸線と水域を復元することにより、今では海から離れた遺跡が実は港として機能していたことから始まり、古墳が海から見られることを考慮して築かれたことや、丸木舟やそこから発達した準構造船が太平洋に広がる航海文化に関係しているのではと言うなかなかに気宇壮大な歴史書である。しかし、日本の平野は本当に最近成立したものであるのだなあと思う。津波で古代の潟湖が再現されてしまったというのは、土地の記憶というのは容易に消すことはできないものであると言うのは実に肯えるものである。2017/11/16
yyrn
11
地理的・土木的な港の成り立ちを知りたいと手に取ったが、古代に関する歴史的な記述も多く、案外そちらの話が面白かった。「海のシルクロード」の終点としての奈良の正倉院に至る海路には、玄界灘の沖ノ島や広島の厳島神社があり、またそのシルクを得るために石見銀山が栄え、時代が下れば岐阜の白川郷の合掌造りで生糸が生産され、維新後は群馬の富岡製糸場で絹製品の機械化が始まると言う世界遺産つながりは偶然ではないのではないかという記述に思わず膝を打った。ナイス!座布団一枚!2017/12/19
コカブ
8
丹後や瀬戸内海を舞台にして、古代の地形を検証し、現在は消滅した潟湖地形を復元して、古代の海運で港として使われた場所を検証する。同様の分析を他の場所でも行っている。冒頭の丹後の個所では、竹野・網野といった海岸沿いの平地に昔は潟湖があったことを検証し、古墳の分布の理由を求める。また、瀬戸内では遣新羅使の記録に残る土地を追って、同様の地形復元を試みていた。そもそも著者はオセアニアの研究をしていて、同様の着眼点を日本史にも持ち込んだようだ。素人目に見ても着眼点は凄いし、ITを使って歴史を解析するのも面白かった。2018/06/09
アメヲトコ
8
北海道から沖縄まで、日本の古代の港についてさまざまな角度から語った一冊。割とざっくり踏み込んだ推理も多いですが、カシミール3Dを駆使した景観復元などは興味深く読みました。随所に挿入される自身撮影の写真からは、著者が各地を自分の足で精力的に歩き回っていることが窺えます。2018/04/05
イツシノコヲリ
7
古代の港について、瀬戸内海や日本海のみならず、北海道や南西諸島まで幅広く扱っている。カシミール3Dを用いた図がとても分かりやすくてよかった。他にもカヌーの起源や古代の船の構造など興味深いテーマについて語られている。古代の港についての一般書は少なく、「埋もれた港」と「地形からみた歴史」ぐらいしかない。2022/10/14