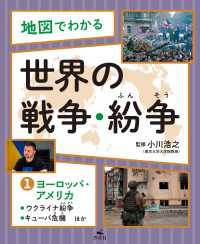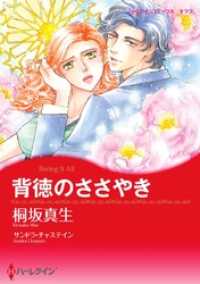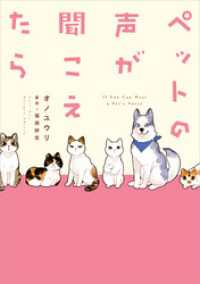内容説明
化粧には、おしゃれ、みだしなみ目的のほかに、身分や年齢、未既婚などの立場を示す機能もあった。古代から現代まで、地域や時代の価値観に左右される化粧の変遷を、メイクアップを中心にたどり、流行の背景となる社会現象とともに探る。時代による美意識の変化や東西比較、メディア戦略にも触れながら、暮らしの中にある化粧の歴史を描きだす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
377
著者紹介によれば、山村博美氏は化粧文化研究家とのこと。巻末の参考文献一覧にはたくさんの書籍が並べられている。ただし、一次資料は少なく、多くは化粧関連の解説書で占められている。この人は努力家で勉強家なのだろうと思う。本としての構成能力もあるだろう。ここで述べられていることにも間違いはなさそうだ。ひじょうにわかりやすく日本の化粧の歴史が語られていると言っていい。ただ、残念ながら著者に独自の視点が見られない。つまり、驚きがないのである。力作だが残念。2023/07/06
シルク
17
学生の時、古代日本化粧史概論みたいな授業を受けた。授業しはるのは超絶人気のM先生(男)。留学生のお土産のチベットの民族衣装を着て、キャンパスを闊歩してたり、大学にチェ・ジウが来て妙なドラマを撮影していた時には、木々の間に潜んでこっそり写真撮影してたりしてた、そんな先生(……)。その先生が、「化粧の始まりは~」とか話し出して、こう言わはった――化粧ってね、まあ魔除けが本来の目的ですわ。人間の体、穴が開いとるところから悪霊やら侵入してくるってイメージね。せやから古代において、化粧してやった巫女達は、魔除けの→2019/12/09
小鈴
16
身近にある化粧は、塗っては洗い流すもののため通史として描く場合、過去になればなるほど記録は乏しい。埴輪や障壁画から類推し、平安以降は絵巻、江戸時代になれば浮世絵や解説書が参考に。但し、江戸時代は子持ちは眉を剃るのが通常だったが浮世絵の子持ちの美人画には眉が描かれるなど常に絵が反映しているわけではない。化粧の歴史は古墳時代から平安前期、平安中期から江戸時代、明治時代以降と大きく三つに区分でき、中国の影響を受けたが国風化し白粉、紅、お歯黒が確立、そして西洋化。日本の特徴だったお歯黒はすっかり廃れてしまった。2016/07/05
りり
15
剃り落とした眉、黒く染めた歯、美顔術、小麦色の肌、美白ブーム、、、化粧の歴史がすごく興味深くて面白かった! 今では信じられない化粧もあって驚きで考えてみたら、怖い。 でも、どの時代も女性は綺麗にしたいと思う心は変わらない。2021/08/16
Sakura
14
大陸の影響が強かった古代から、平安時代には日本独自の化粧へと変化。白(白粉)・黒(お歯黒)・赤(口紅、頬紅)が日本の伝統的な化粧の基本3色とのこと。お歯黒の成立過程は謎が多いようだが、古事記の応神天皇の代にお歯黒を連想させる記述がすでにあったとは。明治初期に来日した外国人には剃り眉、お歯黒は相当気味が悪かったようだ。無理もない。化粧会社の創業、洋風化粧の広がり、白粉から「肌色」の出現から定着、戦時下での化粧、戦後から現代まで、日本の化粧の歴史がわかって面白かった。2024/01/08