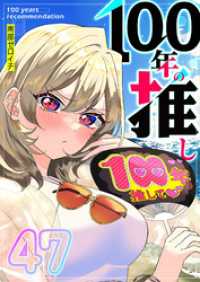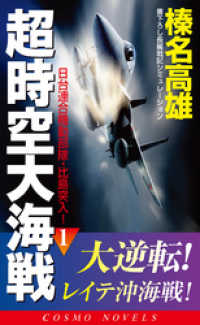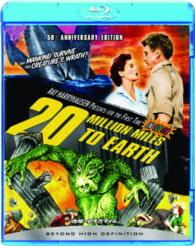内容説明
紀元1~2世紀頃、インドで興起した大乗仏教。それまでの教理を批判し、自利よりも利他行を強調する考え方は広く中国・日本にも及ぶ教えとなった。同時代にその教理は「法華経」「涅槃経」「華厳経」などの経典にまとめられたが、日本では「法華経」「勝鬘経」とともに「維摩経」の三経を仏教の根本として聖徳太子が注釈を加えている。本書の主題「維摩経」はやはり紀元1~2世紀頃の成立とされ、支謙(3世紀)、羅什(4~5世紀)、玄奘(7世紀)らが漢訳するなど、大乗経典のなかでも特に重要な経典であったが、もともとサンスクリット語で記された原典はこれまで存在が知られていなかった。それが2001年、大正大学の研究チームによってチベット・ポタラ宮の書庫でサンスクリット語写本が発見され一大ニュースとなった。その経典のなかで教えを説くのは、在家仏教者でありながら悟りを開いたとされるの「ヴィマラキールティ(維摩詰)」である。病を得た維摩のもとへ、世尊シャーキャムニの指示により訪ねてくる弟子・シャーリプトラ、マハーカーシュヤパや文殊菩薩たち。そこで繰り広げられる弟子や文殊たちと維摩との真理に関する問答。核心にあるのは「空」「煩悩即菩提」の思想であり、菩薩とはなにか、仏国土とはなにかという大問題が展開されるが、それぞれの場面は芝居仕立てによって読む者・聞く者を強く惹きつけていく。本書は、サンスクリット語原典写本からの和訳を引用しつつ、人びとに強烈なインパクトをもたらす大乗仏教の利他行思想を紹介する。
目次
第一章 サンスクリット語写本の『維摩経』
第二章 「煩悩即菩提」という根本認識
第三章 菩薩のありようと仏国土の現れ
第四章 大乗経典は仏説か
第五章 ヴァイシャーリーの大城で――維摩と声聞との出会い
第六章 文殊が維摩を見舞い談論する
第七章 不可思議解脱という難問
第八章 行くべきでない道を行く菩薩
第九章 維摩の沈黙を称える文殊――入不二法門への答え
第十章 園林での世尊・弟子たちと維摩
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
乱読家 護る会支持!
Shinjuro Ogino