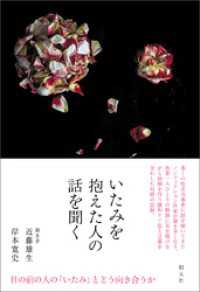- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
人は、後半生になると重荷を下ろしたくなるものだ。西行、親鸞、芭蕉、良寛に共通するのは、人生の折返し点を過ぎ、歌や句に傾倒していったこと。肩にのしかかった責務や思想、人間関係などから解き放たれ、旅に出て「うた」をつくった。孤独を楽しみ、軽やかな自由の世界にあそんだ。『「ひとり」の哲学』に続く、心にしみる人生論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
cape
12
2,000年以上も前のインドの賢者が唱えた「四住期」、「学生期」「家住期」「林住期」「遊行期」。その「林住期」を、旅の空の西行、親鸞、芭蕉、良寛に見る。そこには4人に通じる僧でも俗でもない、変容がある。この見方自体はあくまで著者による想像のもので、事実は異なるかもしれない。おそらく異なるだろう。ただ、この本には88歳の著者だからこその諦観を含んだ達観があり、それが「身軽」になるということ。「つひに無能無芸にして、ただこの一筋につながる」(『笈の小文』松尾芭蕉)、人生の極致なのかもしれない。2019/11/24
coldsurgeon
6
古代インドでは、人生の4段階を想定して、学生期、家住期、林住期、遊行期と名付けた。その林住期は一時的に家を出て、ひとりになって自由な時間を楽しみ生きる時期だ。その林住期を体現したとする西行、親鸞、芭蕉、良寛を順にあげて、重荷を背負ったまま人生を終えるのではなく、身軽になって、解放されて生きることを提案している。しがらみをすべて捨てることが出来るわけはないが、少しでも軽みを漂わせることが出来ればよいか。2022/05/18
良さん
4
古代インドの老賢者が発見した人生の第三ステージ「林住期」について、これが日本人の生き方にもあったとする。 【心に残った言葉】四つの人生段階とは…学生期・家住期・林住期・遊行期(34頁)/西行という存在と親鸞の運命を同時に考えようとする時、「鎌倉」という言葉は要らない。…同じように、親鸞と芭蕉・良寛を並べて想像をめぐらすとき、「江戸」という言葉は障害にこそなれ、有効であるとはとても思えない。(42頁)2019/08/20
akanishi
0
まあ何というか著者の妄想、幻覚を記したもので、読み手としては、困る、というところだろうか。読書中は楽しかったけれども。2020/10/22
ナンテン
0
親鸞、芭蕉、西行、良寛。著者は四名に林住期というキーワードを見出した。彼らの作品や経歴を深く知らずに、タイトルだけでこの本を読んだからであろうか、彼らの生き方や読んだ句、形跡を一読しただけでは理解できなかった。なぜ彼らがこのような生き方を選んだのか、そして後世に語り継がれるような存在になり得たのか。悩みを行動に移し、行脚し、行脚そのものが林住という生き方なのか。2020/01/13