内容説明
天皇、皇帝、王……。君主の呼称とは、「世界史を貫く背骨」である。その国や地域の人々の世界観の表現であると同時に、国際関係の中での「綱引き」の結果なのだ。古代中国、古代ローマから、東洋と西洋が出会う近代に至るまで、君主号の歴史的変遷を一気に概観し、世界史の流れをわしづかみにする。多言語の史料を駆使してユーラシア全域を見据える、いま最も注目の世界史家が描き切った「統治者」たちの物語。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
absinthe
154
君主号について書いた本ではあるが、王権の歴史がなんとなくわかる。何気なくつけられたように見える『王』『皇』『帝』は、日本には歴史上ほぼ天皇が君臨しておりその違いに配慮する必要がなく、普段は意識していなかったという。洋の東西の王と皇帝、そのた王権を示す数々の呼称。何故そのように変わってきたかはそのまま世界の歴史に通じていた。王から始まった歴史。しだいに王が乱立してその言葉の価値が下がると、王を支配する王の意味で皇帝が使われるようになった。西洋の号もその言葉が翻訳として使われる。2021/10/23
kawa
29
「『王』は君主であっても、『皇帝』から任命を受ける下位の地位・称号にほかならない」 君主号を巡って中国・西洋・日本の歴史を論ずる。一読でどこまで理解か自信なしで要再読本だが、各々の興味深い記述が印象的。特に中国史が君主号を通じて大雑把に把握でき興味が持てたことが収穫。本書に刺激されて司馬先生の「項羽と劉邦」の再読にチャレンジ。ヨーロッパの国々と異なる立ち位置の英国史にも興味がわく。2023/05/04
きいち
25
なぜ王の後継者であるチャールズもムハンマド(サウジ)も日本では「皇」太子と呼ばれるのか、という問いから、古代中国、ヨーロッパの君主号の今まで、文化をまたいだ翻訳のあり方を解き明かしていく様はとても面白く、ややこしいのに一気に読める。皇帝は王の中の王、本来的には一つの世界に一人しかいないもの、それが「帝国主義」末期に最も増え、第一次大戦で一気に減少。いま、国際的には唯一天皇だけがエンペラーとされる不思議。◇称号は威信、権威の源。それは資格や学位も変わらない。翻訳とルール作りの大変さも。2019/11/25
さとうしん
12
トリビアルに世界各地の君主号について取り上げるのではなく、取り上げる地域は割と限られているが、中国→西洋→日本と、うまく文脈をつなげてある。王と皇帝の位置づけについて東西で一脈通じているという評価や、天皇については元来「王」号呼称になじんでいたという話、チャールズはなぜ「皇太子」と呼ばれるのかといった話題が面白い。2019/10/17
バルジ
9
「君主号」に着目し各地域の歴史の流れを概観できる稀有な一冊。否応なく政治性を帯びる君主号に着目して東洋・西洋・日本の秩序体系を比較する試みは成功していると言ってていいだろう。特に面白いのが「皇帝」号をめぐる各地域の捉え方である。一元的なユニバーサルな存在であった東洋の「皇帝」、「皇帝」が乱立する多元的な状況が許容され、しまいには「王」との差異が消え去った「皇帝」、日本はそもそも「皇」と「王」の区別が曖昧だったそう。どうやら現在の「国王」「皇太子」という呼称の捻れもこのあたりの曖昧さに一因があるらしい。2020/06/21
-

- 電子書籍
- 人妻の唇は缶チューハイの味がして(22)
-

- 電子書籍
- 私を恨んでいる元使用人にどうやら復讐さ…
-
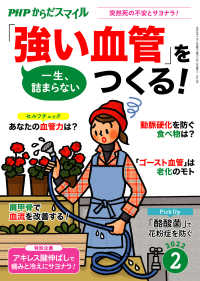
- 電子書籍
- PHPからだスマイル2022年2月号 …
-
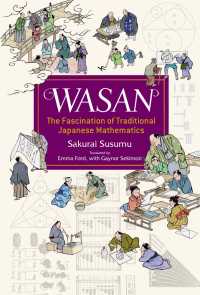
- 電子書籍
- Wasan, the Fascinat…
-

- 電子書籍
- BikeJIN/培倶人 2015年12…




