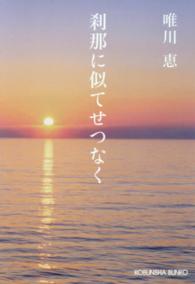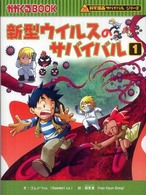内容説明
本書は次のような狙いでつくられました。「理科の時間に習ったけど忘れてしまったり、理科の授業では『そんなことは当たり前のこと』と決めつけられていたり、『これを扱ってしまうとややこしくなる』といった理由でスルーされてしまったりして、ずっともやもやしている事柄を解決したい……!」たとえば、電流の直流と交流って、何が違うのか説明できますか? 乾電池では、プラス極、マイナス極があって、電気を使うものをつないだとき、電流はつねにプラス極からマイナス極に流れます。このように、電流の向きや大きさが変化しない電気を直流といいます。一方、コンセントからとれる電気は、ある一定の周期でプラスとマイナスが入れ替わって電流の向きが変化し、電圧もその周期で変化しています。このような電気を交流と呼ぶのです。そのほか本書では、「高気圧だと晴れるしくみ」「惑星はなぜ『惑う星』なのか」などのモヤモヤがすっきりします。理科の謎を楽しみながら納得感の得られる一冊です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鯖
24
理屈も分からないまま、電子はマイナスからプラスに流れるとかただ丸暗記してた文系のための本。交流は目まぐるしく電気の流れが変わるが、直流は一定。発電所では電磁誘導によってコイルを回転させて電流を得るが、回転のたびに+と-が入れ替わるので交流の電流が得られる。交流の電気のほうが電圧の変換が容易で長距離を運ぶのに適しているため、交流のまま電流を運び、ご自宅のACアダプターで電化製品にあわせて電圧を100Vから下げ、電流の向きをそろえるとのこと。著者と発電所のみなさんとACアダプターありがとうありがとう2019/12/15
栗羊羹
10
酸性とアルカリ性の違い、直流と交流の違い、フレミングの左手の法則、サナギの中身はどうなっているの?、月の満ち欠けと潮の満ち引きの関係性…などなど…あー!こういうことだったのか!がたくさん。理科の授業では当たり前、でもキチンと聞いておけば良かった…2020/02/29
まっちゃん
1
タイトルに惹かれて、ちょっとした勉強のネタに読んでみようと手に取ってみた本です。高気圧が晴れになる理由や、海水が塩辛い理由、月の満ち欠けなど、自分が学んだことを少し掘り下げていくと、なるほどなぁという種がいっぱいあるのだなぁと思いました。イオンやら、分子やら忘れかけていた知識もいっぱいありましたが、簡単に説明されていて、う~んと言いながらも、読むことができました。もうちょっと高校時代の学びをおさらいしてから読むともっと理解できるんだろうなぁと思いますが、子どもへのちょっとした話のネタにいいなと思いました。2022/08/17
ゆってぃー
1
太陽ー水金地火木土天海(冥王星は外された)、岩・固体タイプは水金地火、ガスタイプは木土、氷タイプ天海。衛星は惑星の周りを廻る星で、例えば月。惑星と衛星は恒星ではなく、太陽の光を反射して輝いている。 2020/04/01
ハイディ
0
分かり易いのだろうけど、良く分からないものもあった。2021/05/08
-

- 和書
- 季節と暮らしの動物刺繍