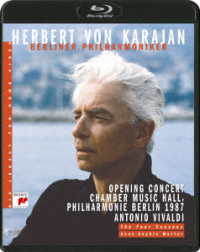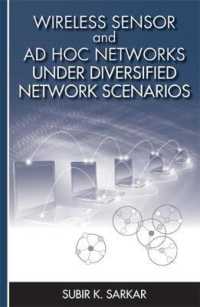- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
地方のコミュニティは衰退し、都市はグローバル化によって格差が拡大し疲弊している。そして都市の論理が地域のコミュニティを崩壊させている──通常このように否定的に語られることが多い。だが本当にそうだろうか。軽やかに移動し、ICTの様々なコミュニケーションの新技術でつながった人々による、都市における新しい共生の作法がありえるのではないか。多様性を認める寛容な精神に満ちた作法が、既存のコミュニティをも変えていく可能性を探る、碩学による最新社会評論。
目次
序章 いま、なぜ都市共生なのか
I 共生
第一章 生きられる共同性――イリイチの「共生」概念
第二章 都市をどう見るか――漱石・ 外・須賀敦子の視座
第三章 多様性と寛容さ――ジェイコブズからフロリダへ
II 多様性
第四章 「美しいまち」と排除の論理――自閉するまちづくりと「異なるもの」
第五章 安全・安心――コミュニティの虚と実
第六章 新しいコスモポリタニズム
III ボーダーとボーダーレス
第七章 サロンとコミュニティ――コ・プレゼンスのゆくえ
第八章 弱さと向き合うコミュニティ
終章 多様性と差異のゆくえ――ポスト都市共生へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
67
複数の書籍に発表された論文と書き下ろしをまとめたもの。第八章にあるように弱者が強者に転換されうる社会(もちろん、その逆もありうるだろう)があっていい。というかむしろそうでなくてはならない。そういった特に下から上への流動性は現代の社会にまだまだ少ない要素であるように思う。年々それが難しくなっているように感じる。ここに寛容非寛容の根っこがあるような。2019/11/06
センケイ (線形)
8
タイトル的には関心にドンピシャだったので一読。具体的な事例もありつつ、新書としては割と理論面もあって往復する形で書かれているのが良かった。終盤、コミュニティの動的側面を重要視しようという議論は、事実観測とべき論が混ざっている感は少しあるかも。ただ、どの論者が何と主張したかという点は明確に拾えるし、着目している視点としてはこれも自分の好みで面白かった。2021/12/04
本命@ふまにたす
3
現代社会のコミュニティや都市が抱える問題について考察。理論、社会調査両方のアプローチが組み合わされているが、既発表原稿を利用しているのもあってか、やや内容が雑然としている印象。2022/10/21
ぷほは
3
それなりに理論的な前史はまとめられているものの、そこまで体系性や一貫性があるわけではなく、どこか議論が上滑りしている印象があり、途中まで読んで寝かせていた。バリ島の街路樹の事例におけるまちづくりが持つ自閉性と、ダウン症の子供を持つ母親の視点から語れるコミュニティ形成における「弱さ」の重要性については、本質的な論点を提供しているように思えた。しかしやはりこれらを解釈する枠組みがどうも的を射ているように見えず、一歩前の世界観を眺めている気分になる。コロナ以前、2020年代以前の時代とはこういうものだったかと。2022/01/05
まあい
3
「異なる他者」に開かれた都市共生へ向けた論考。現代社会に関する理論や思想と、ゲーテッド・コミュニティや被災地のサロンの事例とを往還する議論で、さまざまな示唆に富んでいる。無条件に「居合わせること」(コ・プレゼンス)、「情動的な紐帯」、などのキーワードを軸に、さまざまなスケールのコミュニティについて考えてみたくなる。なお本書は、既発表論文をもとに編集者の前で口頭発表する、というプロセスで書かれているため、同氏の他の著作よりも読みやすい。2020/02/19
-

- 電子書籍
- 蝶々遊び 7巻 コスモス
-
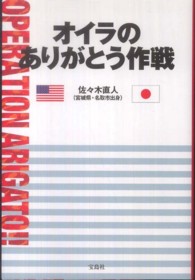
- 和書
- オイラのありがとう作戦