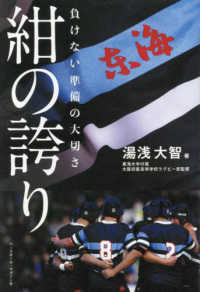内容説明
美しいメロディを奏でる「論理」と「数理」とは? フランス音楽界で絶賛された作曲家・演奏家が語る「作曲のロジックとテクニック」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
37
全く酷い本だ。「科学」という言葉と、講談社ブルーバックスを信じて手にした自分がバカだった。内容は、楽理の本の1ページ目のような当たり前のことを、さも大げさに説明するだけだし、楽器の紹介も、極めてお座なり。私は、音楽(特に楽理)は数学だと思っているから、このタイトルに期待したが、この本のどこに「科学」があるというのか。ショパンのことを「あえてテクニックをひけらかすような難解な曲を書いて」などと言う著者を、私は信じない。ブルーバックスは好きなシリーズだけど、この本は酷い。心の底から怒っている。2019/11/20
Fondsaule
22
★★★☆☆ デュボワ先生が、基礎の基礎から、協会旋法のイオニア旋法、ドリア旋法、フリギア旋法、リディア旋法、ミクソリディリア旋法、エオリア旋法、ロクリア旋法 まで教えてくれる。2022/05/27
あや
20
著者はマリンバ奏者でフランス人。ごく基礎的な音楽知識から五線譜に曲を描くまで記述あり。私は中学校の作曲の宿題でくらいしか作曲をしたことがない。毎日お風呂ででたらめソングなら歌っているが。今年は作曲をしてみようかな。五線譜に書くのが面倒だったら電子ピアノで弾いたものをボイスレコーダーに録音するのはどうだろう。今年やってみたいことのひとつにしてみます。2026/01/03
み
15
音楽やってる身からすると、楽典も基本小学生あたりでほぼ覚えてしまったので、真新しい知識はそんなに入ってこなかった。初学者向けだと思う。2022/10/09
MASA123
11
この本は、参考音源が特設サイトから聞くことができる。CD付きだとこの値段(税別1000円)では販売できなかったと思う。まあ、便利な時代になったものだ。 作曲の科学、というほど理系理論的な内容ではなくて、前半2章は、「楽典」の入門書のようで、トニック、ドミナント、サブドミナントの解説とか、わかりやすかった。 後半2章が、作曲手順のような内容で「あなたも、○○時間でギターが弾ける」的な感じだった。最終に、模範事例的な曲が用意されていて、特設サイトから聞いてみたが、なんだか凡庸な感じだったけど? 2024/01/09