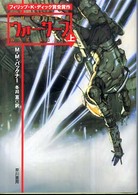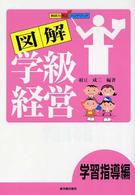内容説明
日米地位協定は、在日米軍の基地使用、行動範囲、米軍関係者の権利などを保証したものである。在日米軍による事件が沖縄などで頻発する中、捜査・裁判での優遇が常に批判されてきた。冷戦後、独伊など他国では協定は改正されたが、日本はそのままである。本書は、協定と在日米軍を通して日米関係の軌跡を描く。実際の運用が非公開の「合意議事録」に基づいてきた事実など、日本が置かれている「地位」の実態を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
007 kazu
31
在日米軍の基地使用、行動範囲、米軍関係者の権利を保証した日米地位協定と前身である日米行政協定について。序盤は歴史的経緯の概説、その後、米軍が駐留するNATO国との比較でその違いを示し、著者ならではの問題提起や解決策を提案しており読み甲斐のある一冊。沖縄では米軍機の墜落や米兵による凶悪犯罪が起きるたびに問題になるが協定通りの運用がなされていなかった。元凶に「密約」に等しい「日米地位協定合意議事録」の存在を指摘し、本議事録に依る(米軍にとっての)なんでもありの運用されてきた事実を指摘していることに価値がある。2021/09/02
hatayan
31
沖縄で米兵が暴行を働いても日本の法で裁かれないのは、在日米軍の地位を記した「日米地位協定」が根拠。協定締結の際に作られた非公開の議事録が米軍の地位と特権を温存、日本に裁量の余地は乏しく米軍に有利な仕組みになっていることを成り立ちから解説します。 中盤では、駐留軍を主体的に規制できるドイツやイタリアと比べると日本の米軍への気遣いが際立つとの指摘も。 協定の見直しが国内世論で高まっても、米国での政策上の優先度は低く温度差は埋めがたい。だからこそ、日米地位協定は沖縄だけの問題ではないことを意識したいと訴えます。2019/09/19
James Hayashi
27
琉球大専任講師、国際政治史専攻、19年著。米国軍人、軍属がレイプ、殺人、事故など日本でやらかした時取り上げられる日米地位協定。その生い立ち、歴史、中身など網羅し、日本が置かれている実態を描いている。 選挙戦でも各政党が地位協定の改訂を謳っているが、実行に至らず。地位協定は日米だけのものでなく、米国は115ヵ国以上と締結している。やはり各地で問題になっており、各地で改訂もしくな補足協定で不平等さを訂正してきている。日本は安保、防衛の問題があり、議論が盛り上がっても沸騰しきらず。→2020/05/21
coolflat
25
なぜ日米地位協定は、在日米軍に幅広い行動の自由を与えているのか。その起源は、1951年のサンフランシスコ講和条約を締結する際、独立後も引き続き米軍の駐留と基地の使用を認める日米安保条約と日米行政協定を結んだことにある。日米行政協定は、1960年の安保改定の時に日米地位協定へと全面的に改定された。しかし、在日米軍の既得権益の両柱である基地の管理権と裁判管轄権・捜査権については、日米行政協定の内容が日米地位協定へと実質的に引き継がれている。もっというと、表には見えない“運用”という形で引き継がれている。2020/10/22
風に吹かれて
22
日米地位協定(1960年制定)は日米安保条約を基に在日米軍の施設・区域と合衆国軍隊の地位(例えば、米兵が犯罪を犯したときの取扱い)を定めたもので、日本は条約として扱っている。問題は、「日米地位協定合意議事録」なるものの存在。「議事録」の内容は国会ではほとんど論議されていない。米軍が「必要と認めれば」昼夜を問わず自由に戦闘機やオスプレイが日本中を飛び回れるような合意が行われており、住民の生活を脅かしている。 →2023/06/01
-

- 電子書籍
- 週刊 東京ウォーカー+ No.22 (…
-

- 電子書籍
- Harlem Beat (8)