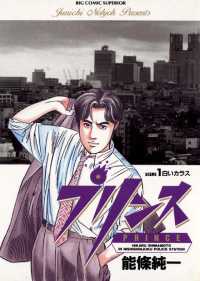内容説明
著者が30年間惚れ続けている大江戸歌舞伎。誰も見たことのない100年以上前の歌舞伎とはどんなものだったのか? 歌舞伎の定式、専門用語とは? “時代”と“世話”とは? 顔見世狂言とは? などなど、江戸の歌舞伎の構造を徹底解説。人気狂言『兵根元曽我』はなぜ何ヶ月も何ヶ月もロングランしたのか?? 粋でイナセでスタイリッシュな江戸歌舞伎の世界へようこそ。
目次
歌舞伎の定式/江戸歌舞伎の専門用語/江戸歌舞伎と曽我兄弟/東と西と/江戸の時制―時代世話/歌舞伎の時代錯誤と時代世話/顔見世狂言とは何か/顔見世狂言の定式/江戸歌舞伎と“世界”/江戸歌舞伎の反逆者達/江戸のウーマンリブ/江戸の予定調和
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sawa
9
☆☆☆☆ 江戸時代から現代までの歌舞伎史ではなく、江戸の歌舞伎だけを扱った作品で、詳細なのに、こんなに分かりやすく、軽いタッチのものは珍しいのではないだろうか。復活通し狂言で、時代物から始まるのに世話物が挟まるのをなぜだろうと思っていたが、これを読んでよく分かった。あと、近松門左衛門を始めとした上方の狂言作者は、「けいせい~」という作品をいくつも書いているのだが、傾城(遊女)とは関係なくただそれを付ける「決まり」だったといのには驚いた。その大らかな感じが好きだ。2011/02/17
みつひめ
7
単行本も持っているのに、読み始めるきっかけを逸してしまい、積ん読に。文庫版なら、持ち歩けるからと、買い直した。ずーーーっと疑問だった、江戸の通し狂言の構成が、一発でわかった。こんなことなら、もっと早くに読んでおくんだった…汗。実は、長い版があるとのことなのだけれど、それも読んでみたい!2013/05/21
kishikan
6
江戸歌舞伎の解説本でも歌舞伎を論じた学術書でもない、といっても歌舞伎に興味を持つ者にとっては非常に興味深い読物です、これは。江戸時代といえば、今日の歌舞伎が生まれ、そしてほぼスタイルとして完成した時代ですから、その形と当時の社会を関連付けたこのような読物は歌舞伎好きにとっては非常にためになります。今度は続編で、それぞれ出し物についても、詳しく取り上げて欲しいものです。2010/10/31
よの字
5
江戸の歌舞伎を「今」に引き付けて語るのではなく、当時の文脈で理解して行こうという姿勢に頭が下がる。2010/08/19
ドイツ語勉強中
4
これは最高に面白かった!江戸時代の歌舞伎について解りやすく丁寧かつ大まかに(ここポイント)説明してくれている。初心者として、『歌舞伎手帖』とこれがあれば、かなり基礎知識が付くのでは。あとがきがまた良い。何故歌舞伎を好きなのか?橋本氏の考え方が素敵だと思った。久しぶりに、作家読みしたい人を見つけた!2015/02/15