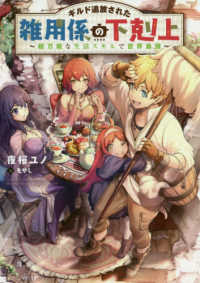内容説明
終戦期に邦人がいかに復員を果たしたかは、これまで個人史のかたちで主観的ながら広く伝えられてきた。しかし近年旧連合国の資料公開が進む中で、引揚の全体像を客観的にとらえることが可能となってきた。本書は、最新史料をもとに謎の多かった東南アジアにおける抑留と復員の実態を明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nnpusnsn1945
42
田中宏巳氏の研究と重複する部分はあるが、南方(ビルマ、タイ、マレー、シンガポール、インドネシア、東部ニューギニア、フィリピン)における日本軍将兵の抑留、復員について取り扱っている。シベリア抑留よりきつくはないと思われがちだが、実は捕虜の担当に当たった地域や連合国、作戦地域ごとに差があり、待遇が劣悪であったり戦犯裁判が多い等の事情もあった。また、植民地支配の問題も絡んでおり、著書はインドネシアを除いて失政であったと評している。2022/10/03
Toska
15
南方(東南アジア〜ニューギニア方面)からの引き揚げを取り上げた労作。抑留者の数はシベリアに倍し、最終的な引き揚げは1948年になるまで完了しなかった。また、日本人捕虜に強制労働を課そうとする英蘭と、これに反対する米国との間で深刻な政治対立も生じている。シベリア抑留の悲劇が繰り返し記憶に蘇るのに対し、南方での出来事がよく知られていないのは、冷戦の中で対ソ関係に意識が集中した副産物であろうか。2024/07/16
の
4
南方日本軍兵士の抑留・強制労働・復員の全体像を明らかにする本。120万人の軍人・民間人が戦後ビルマ、インドネシア、ニューギニア、フィリピンなどに抑留され、しかも復員終了まで2年半も要した。英国軍やオランダ軍はジュネーブ協定に基づく「戦争捕虜」ではなく「降伏者」と見なし、日本による捕虜生活の恨みを晴らすべく過酷な労働を強いる。これに対しマッカーサーは国際的義務の履行を求め、英国側に賃金の支払いと復員の圧力をかけ続ける。抑留者は自給自足生活を徹底させ本土の負担を減らす。人間的要素の重要さは各々の思惑に現れる。2019/09/24
侍の笛1吋
2
最近、本を読む気力が無くひさびさに読み終わりました。 終戦時の日本軍捕虜に関する物だとシベリア抑留が良く出ているが、シベリア抑留者が約69万人に対して南方での捕虜は120万人 捕虜を管理する戦勝国イギリス オランダ 米国 米国を除くイギリス オランダはかなり厳しい扱いを受けたようだ。 ただ米国が管理したフィリピンの戦没者はフィリピンに派兵された兵隊の8割 まさに運隊2019/10/01
takao
1
ふむ2025/04/13