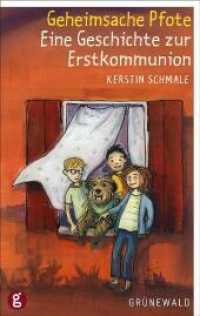内容説明
東京~京都間はなぜ中山道ではなく東海道で結ばれたのか? 御殿場と並ぶ、山陽本線の難所「瀬野八」が誕生した理由は? かつて北九州に約一週間だけ存在した幻の巨大駅とは? 普段私たちが何気なく利用している全国の鉄道路線は、実は知らないことばかり。日本近代史に精通する著者が、その成り立ちと残された謎を史料と地図を駆使しながら徹底的に深掘りする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
69
もし明治初期、貴方が日本白地図とペンを渡されて鉄道をどう敷くか?と問われたらどう線図を描き入れるか?そんなことを考えながら本書を紐解くと良いかも。そこには、経済性・政治・軍事の思惑が絡むのは必須。地形や等高、工法やその技術力検討も必須。僕は竹内氏を本書て初めて知ったのだか、これらをよく調べられていて物凄く知的好奇心満たされたのである。中山道ルートか東海道線ルートかから始まり米軍の爆撃を見据えた関門海峡トンネルとその米軍の作戦に至る迄。読了し、竹内氏に問いたい。まだネタありそうで続編を希望したいのです。2020/04/12
skunk_c
40
千葉の京成新線やアメリカ軍による関門トンネル爆破計画など、初めて知ることもあったが、全体に冗長な印象。基本的に内陸線を作りたい陸軍vs経済効率(特に港との関係)から海岸沿いに鉄道建設したい財界という対立さえ押さえれば、あとは実際の路線がどうだったかを地図で示せばよく、もっとしっかりした地図が欲しかった。特に河川とその名称や峠、できれば主要国道などが地図に明記されていないのが残念。また気になるのは元号表記で、やはり西暦併記して欲しかった。特に国際事件が絡む大正~昭和期はかなり読みづらかった。2019/09/03
てつ
34
ふしぎな、と命名されているが、れっきとした地形学と鉄道の歴史を事例で論じた本格的な本。当時の文書が多少手を加えながらも引用されて、その後に意訳されている。これが少し冗長な気もするが、かえって丁寧にも感じられて面白い。鉄道好きの方だけでなく地形と歴史の関係を知るのにも適した良書です。2024/07/20
きいち
33
軍事から見た鉄道建設史。西南戦争や日清戦争の兵員輸送に占めるその効果の大きさと、一方で、執拗に艦砲射撃のリスクを気にして経済的にもその兵員輸送の面でもコスト高の内陸を通らせようとする陸軍の影響。近代国家草創期、資金繰りなんとかしながらの時代にできていた合意形成(井上勝や渋沢栄一がバランス)。それがどんどん消えていく様に『失敗の本質』が思い起こされた。2019/08/25
yyrn
22
最近の道路は直線的だが、昔からの道路は地形に沿って緩く曲がっている場合が多く、それだけでも歴史を感じさせるが、では明治初期から慌ただしく始まった鉄道線路の場合はどうか?東京と関西を結ぶルートは当初、東海道ではなく中山道が考えられていたという話から始まって、大消費地と各生産地を結ぶ本線や輸出港につなぐ線路などの話が続くが、それらの2点間を結ぶルートが、どんな理由からそう決定されたのか?もっとふさわしいルートがあったのでは?と思える不可思議なルートの数々について、過去の資料の中からそれらを解き明かしていく。2019/10/20
-

- 電子書籍
- 宝石姫は、砕けない ~毒親にネグレクト…
-
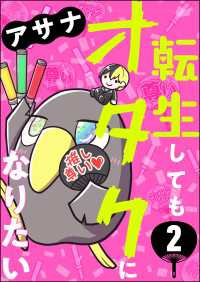
- 電子書籍
- 転生してもオタクになりたい(分冊版) …
-
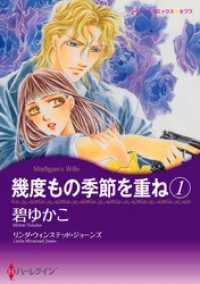
- 電子書籍
- 幾度もの季節を重ね 1【分冊】 1巻 …
-
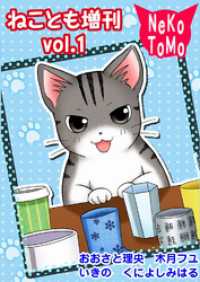
- 電子書籍
- ねことも増刊vol.1 ペット宣言