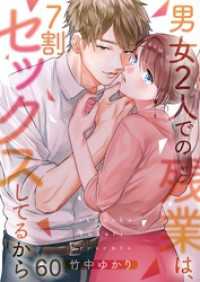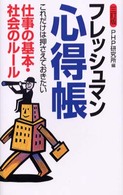内容説明
自治体職員が自分たちで地域を変えるために不可欠な課題の発見、調査と分析、政策の立案の仕方がわかる!
全国のさまざまな自治体で研修講師を務める著者が、人口推計表を使った課題分析の仕方、まちづくり白書の作成方法、住民ニーズのとらえ方など政策づくりのためのオリジナル手法を紹介する。
目次
第1章 まちを元気にするとは?
第2章 まず、“足元”を見つめる
第3章 地域の課題を見つける
第4章 政策形成=シナリオを練る
第5章 政策実現への気運を巻き起こす
第6章 地域変革の新しい考え方を掴む
第7章 協働のまちづくりの基礎を固める
第8章 自学のすすめ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
黒ハリ
2
これまで思い描いていた「公務員像」を正すことになった1冊(過去に著者の研修を受講したことによるところが大きいか)。職務員と公務員、なるほど。今の自分は職務員としては頑張っている(と思っている)が、果たして公務員たり得るか、否。。完璧な公務員はどれほどいるだろうか。。まちをフィールドワーク:今後頭を使いながら歩いてみよう。わたし的要覧・まちづくり白書作りも、ぜひやってみたいと思う。でもまずは、総合計画のすべてを読み込むことから始めよう!2014/08/18
kesu
1
「公務員力」の考え方が勉強になった。自分の事務分掌に掲られる仕事ができるだけでは「職務員」であり、まち全体に目を向け関心を持ち問題意識を持つことが真の「公務員」である。実際にこの域に達している人は少ないと思うが、常に自問自答していきたい。 「補完性の原理」について、行政側の理屈であって住民側には本来関係がなく、社会的弱者に対しての要望に耳を傾けなければ行政としての役割をはたせていないという話も耳が痛い。「行政」の意義について再考したい。2022/07/18
よムタロウ
0
公務員の宣誓書で公務員として、職務員としての2側面で宣誓した。課の職員として採用された者はいないので、前者として政策形成は身につけておくべき能力 総合計画は事業計画と経営計画。後者は、協働、行財政、男女共同参画、公聴広報など2024/05/11