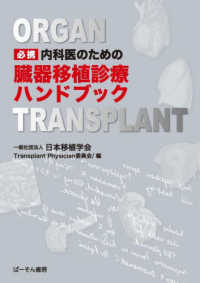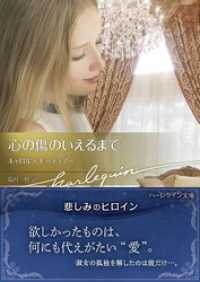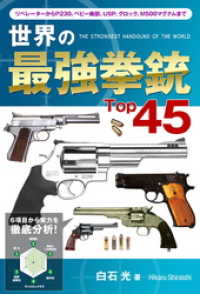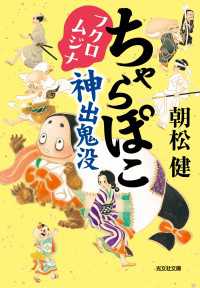内容説明
京のぽっくりの音や蛙の声に古き日本を聴き取り、三島由紀夫、永井道雄ら当代の文豪・知識人に新鮮な刺激を受けた青春の日々。若き米海軍通訳士官から希代の日本文学研究者に至るまでのひたむきな道程。ドナルド・キーン前半生の自叙伝。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
70
日本語の勉強を始めてから、大戦、大学を経て、研究者となるまでの軌跡。日本研究の道を捨てようとまで思いつめたことがおありになることに驚いたし、何より留学したイギリスと日本で出会ったひとたちの高名さにもびっくりする。出会いとはこちらが引き寄せるものなのか、あちらから両手を広げてやってくるものなのか、両方かみ合わないとこのような奇跡は起こらない。三島由紀夫との友人関係においての後悔も綴られ、胸が痛くなる。英米における日本研究黎明期の記録としても読める。昔は大学もおおらかだったようだ。2019/05/15
ホークス
41
元本は1993年刊。日本文学を研究したキーン氏の自伝。印象的な話が多い。一つは、新米翻訳官であった大戦末期に、ガダルカナルで日本兵の遺体から回収された日記帳を解読する話。血の匂いを放つ日記群について簡潔に厳粛に語っている。もう一つは狂言師が発語の締めくくりに使う「御座る」にいい知れぬ魅力をおぼえ、愛嬌さえ感じたという一節。「愛嬌」とはなるほどなあと思った。悔恨の話も多い。友人だった三島由紀夫の自殺の予兆に気づけなかった事。母親との関係をついに改善できなかった事。誰もが重い荷物を抱えていると改めて思う。2022/08/12
彼岸花
17
25年前に完成した自伝です。高尚な訳で、まるで論文のようでした。(その後もご活躍は続く)キーン先生の人生は、日本との歩み、そのものです。「運命」に導かれ、日本文学者としての道を選択されたこと…戦争体験だったり、源氏物語であったり。(未読ですが、ウエーリ氏の英訳が気になります)改めて、日本とアメリカの相互理解のために、尽力なさった方だと思います。多くの日本人作家との交流もあり、広い人脈に、驚きでした。誠己さんの解説では、父親を敬う姿がとても印象的で、幸せな晩年を過ごされたのではないでしょうか。2019/10/10
Takanori Murai
16
たまたま日本語を学ぶ流れで海軍へ、全く戦意を持たずに太平洋戦争の最前線を歩いた。日本軍ならありえない存在。戦後の日本での暮らしは、充実したものだったようだ。最後の三島由紀夫とのエピソードについては感慨深いものがある。題名は芭蕉の言葉から。そんな人生を歩んでこられたんですね。2019/08/13
わらわら
9
「ついに無能無芸にしてこの一筋につながる」松尾芭蕉の笈の小文の中での言葉を引用してタイトルにした、あとがきに説明が自分の一生には変わらないものがずっと連がっていた~~。この説明で本のすべて頷ける。太平洋戦争中、通訳海軍兵を志願して沖縄に、別の視点から沖縄戦を感じた。捕虜の人とも長年付き合う友になる。日本人としての私が学ぶことが多い、書かれている書物、人物、言葉を調べながら読み進める。ずっと一筋に追っているもの愛しているもの私にはあるのだろうか。ドナルド・キーン氏の気持ちが好きです。また本を読んでみよう。2022/08/29