内容説明
人はなぜ逃げ遅れるのか
「あと少し早ければ助かった命もある。
情報やノウハウだけでは人命は助からない。
大災害時代を生き抜くための「新常識」がここに!
「平成30年7月豪雨」別名、西日本豪雨。
このまだ記憶に生々しい災害において、14府県で200人を超える死者が出た。
岡山県倉敷市の真備町地区では、河川の堤防の決壊による大規模水害で、
約4600棟の家屋が全壊し、51人が亡くなった。
その一方で、真備町に隣接する総社市下原地区では、
浸水とそれに伴う工場の爆発という二重の被害に見舞われながら、
迅速な全戸避難を実現して、ひとりの犠牲者も出さなかった。
なぜ人は逃げ遅れるのか。
正しい判断は何に基づくべきか。
生き延びられた理由は何だったのか。
気象現象の「局地化」「集中化」「激甚化」が叫ばれ、従来の常識が通じなくなっている昨今、
「大災害時代」をいかに生き抜くかに迫る。
2018(平成30)年7月に発生した「西日本豪雨」は、
全国で200人以上の死者を出した。
被害が広がった要因はいくつかあるが、そのひとつに「逃げ遅れ」がある。
避難率を見ると、たとえば広島県では、避難勧告・指示が最大で236万人に出されたが、
このうち避難所への避難が確認されたのは1万7000人余 り(0.8%)に留まった。
人はなぜ逃げ遅れるのか。そして、いざというときに迅速に避難するにはどうすればいいのか。
気鋭のノンフィクションライターによる渾身のドキュメントで被災現場をリアルに再現するとともに、
災害心理学や気象学の専門家へのインタビューも収録。
大災害時代のサバイバルに必須の一冊。
[目次]
序 章 生活の消えた町
第1章 西日本豪雨の被災地を訪ねて
西日本豪雨 概要
事例1 岡山県倉敷市真備町有井地区
事例2 岡山県倉敷市真備町川辺地区
事例3 岡山県総社市下原地区
事例4 広島県広島市安芸区矢野東 梅河団地
第2章 人はなぜ逃げ遅れるのか
第3章 生き延びるためにすべきこと
第4章 ポスト災害 ~町と人の再生に向けて~
終 章 人とのつながりを土台に
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
♡ぷらだ♡お休み中😌🌃💤
鯖
栗羊羹
ふたば
toriarii
-

- 電子書籍
- 冥界の超越者、アカデミーへ帰還する6話…
-

- 電子書籍
- 魔王学園の反逆者~人類初の魔王候補、眷…
-

- 電子書籍
- 転生令嬢、結婚のすゝめ~悪女が義妹の代…
-

- 電子書籍
- 君と僕の、漂流する日常17
-
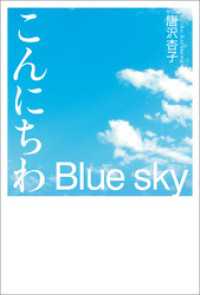
- 電子書籍
- こんにちわ Blue sky




