内容説明
ルターに端を発する十六世紀ヨーロッパの宗教的動揺は、イエズス会というまったく新しい組織を生んだ。霊操と教育を重視し、異教徒への宣教を実践するイエズス会は、ポルトガル・スペインの植民地開拓と軌を一にして、新大陸やアジアへと進出した。かれらの思想や布教方法はどのようなものだったか。いかなる経済的基盤に支えられていたのか。現地社会に与えた影響や「キリスト教の世界化」のプロセスを詳細に検証する。
-
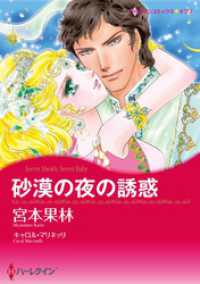
- 電子書籍
- 砂漠の夜の誘惑【分冊】 2巻 ハーレク…
-
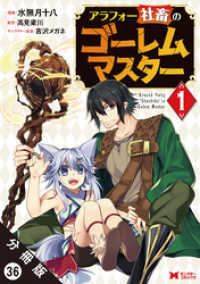
- 電子書籍
- アラフォー社畜のゴーレムマスター(コミ…
-
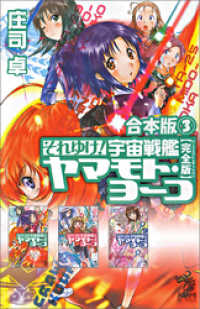
- 電子書籍
- 合本版(3) それゆけ! 宇宙戦艦ヤマ…
-
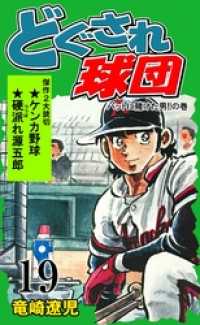
- 電子書籍
- どぐされ球団 19 マンガの金字塔
-
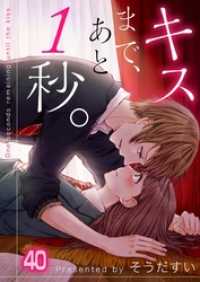
- 電子書籍
- 【フルカラー】キスまで、あと1秒。40…



