- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
幸福度高い従業員は生産性が3割アップする。
「働き方改革」という言葉があちこちで使われるようになったが、実際に職場で何か改善されているという実感が持てない、という声も聞こえてくる。
アメリカの研究では、「幸福度の高い従業員の創造性は3倍、生産性は31%、売上げは37%高い」というデータもあり、世界で「幸福度」は科学的に分析され、ビジネスに取り入れられている。
それを考えればこれからの時代、トップダウン式の組織は生き残れず、リーダーは調和型で、可能な限り部下に権限譲渡し、働き方は個人の裁量に任せるような仕組みにしなければ業績は上がらない。
日本企業は「社員の幸せ」について、何を取り違え、何に躓いているのか。
また、社員が幸せになるとどう成果や業績に変化が現れるのか。
「幸福学」の日本の第一人者・前野隆司慶大大学院教授が、取材を重ねて得たデータを公開、ヤフー、ユニリーバほか、「幸福学」をベースにした職場の変革で業績アップした実例を現場の声と共に紹介する。
職場の改革レッスンも掲載しているので、今日からすぐ実践できる。
-

- 電子書籍
- 私をセンターにすると誓いますか?(4)
-

- 電子書籍
- 回帰したついでに復讐します【タテヨミ】…
-
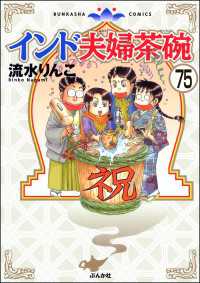
- 電子書籍
- インド夫婦茶碗(分冊版) 【第75話】…
-
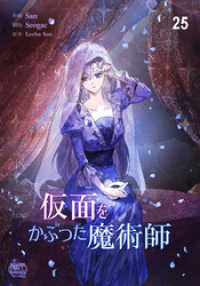
- 電子書籍
- 仮面をかぶった魔術師25 NETCOM…
-
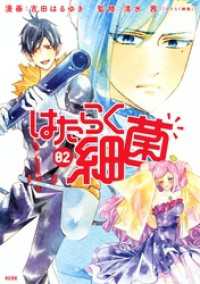
- 電子書籍
- はたらく細菌(2)



