内容説明
「スタンダード」とは本来は標準語のことである。しかし、「標準語」というと、たいていは、明治以降の「標準語」を思い浮かべるだろう。現在、アナウンサーがしゃべっている言葉、東京山の手の言葉などと言われるあの言葉だ。ところが、本書では、江戸期以来、一貫して「話し言葉の標準形態」つまり「標準語」があったと考えている。これを、一般にイメージされる「標準語」と区別して「標準形(スタンダード)」と呼ぼう。書き言葉にも、標準形があった。これも、歴史をたどれば、室町時代までさかのぼる。書き言葉を書く際の表記にも、標準形はあった。これも、明治維新と供に成立したものではない。いわゆる、仮名遣いの問題である。時折言われるように、歴史的仮名遣いは正しいのだろうか。いや、江戸期には、もっと多様で柔軟な表記を許すスタンダードがあった。このようにして、「スタンダード」と言うことを軸として、本書は話し言葉、書き言葉、仮名遣いの歴史に分け入っていく。豊饒な言葉の世界を堪能してください。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Myrmidon
3
話し言葉、書き言葉、表記法(仮名遣い)のそれぞれに関する「標準形(スタンダード)」の形成を、歴史的に述べる。これまでなんとなく、所謂「標準語」や「歴史的仮名遣い」などは明治期に政府主導で定められてきたように考えてきたが、筆者の主張によると、中世~江戸時代にかけてもある種の「スタンダードな言葉」という意識は存在し、例えば現在の話し言葉の「標準語」は、東京山の手の地方語が「標準語」として定められた訳ではなく、「標準語」を話す人々が山の手に住み着いたのだという。2019/09/21
こたろう
3
現在の日本語の話し言葉・書き言葉になるまでを歴史的な観点から読み解こうとした本。話し言葉についての記載もあるが、実際に記録として残せるのは、書き言葉のみなので、本書の大半が書き言葉に関すること。対象の時代としては、室町〜江戸・明治あたりがメインとなる。昔の文書として例示されるのは、やはり和歌などが主体となり、それは庶民の言葉なのか?と思ってしまった。昔の人も漢文を(少し)知っていることの衒学的な行為として無理矢理言葉を音読みしたりしていた様で、人はいつの時代も変わらないと思った。2019/09/18
紅林 健志
0
「東京の山の手の人の言葉が標準語になった」という通説をひっくり返す本。そもそも東京の山の手は、大名屋敷を引き払った後に地方の人々が入り込んだ場所だった。そもそも山の手の人の言葉は「標準語」だったという話。すごい。 その他、中世の軍記の語りについての指摘や、明治の植字工が古言梯を使って、仮名遣いを直していたという話も興味深い。 非常に刺激的な内容の本。ただ、第Ⅱ章の時代を遡っていく叙述がちょっとわかりづらかった。2021/06/15
尋hiro
0
難しかったが、なんとか読み終えた。2020/12/06
-
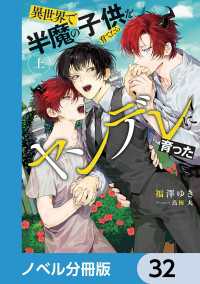
- 電子書籍
- 異世界で半魔の子供を育てたらヤンデレに…




