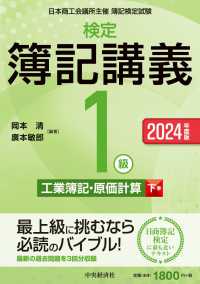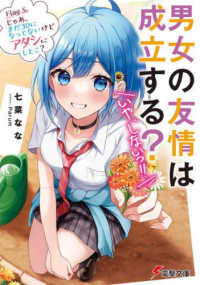内容説明
軍事研究には携わるべきではない、というのは科学倫理の重要テーマである。歴史考察からAI兵器まで若き科学者に向けた書き下ろし。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
47
軍事研究と民生研究。この言葉を知っている若者はどれだけいるのか?また、戦争は発明の母である、という言葉も。本書はそんな現代の我が国にその警鐘を鳴らす一冊。原爆の研究等史実の例示を述べ、愛国心の推移から来る軍事研究への傾斜やその必要資金である国家予算にも言及する。軍の研究や人脈の探索や入り方についても述べる。そして啓蒙と警鐘を述べる。平時慣れし過ぎている我が国で研究者のみならず我々も普段通達だから等丸呑みするいつのまにか染み付いた習慣を捨て去り、悪法なら悪法と述べていく習慣がなければと方策を述べる。2019/09/29
zoe
16
2019年。地球温暖化が悪化するから、息を止めていてもらってよいですかと言われているくらい息苦しい本。自動車やドローンが移動手段や攻撃手段として使われているし、現実に起こった戦争を見れば、論拠としたものは相当失われている。戦争反対の誰もが戦争目的で研究をしていないが、研究成果がことごとく世界中で戦争に加担しているとしか言えない状況なのでは。だとすれば、戦争反対研究者の権利を守るためにも、あるところで切り離す制度(特許非公開もその一つでは)が必要で、それを研究への介入と言われると、私のようなひたすら平和を→2024/09/08
Susumu Kobayashi
9
大学で軍事研究はタブーということは知っていたが、日本学術会議が1967年に「軍事目的のための科学研究を行わない声明」というのを出していたことを知らなかった。こういうことはもっと周知しなければ、ぼくより後の世代は知らないだろう。防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」が研究者を取り込もうとしていることもよくわかった。理想的には科学者全員が軍事研究に手を出さなければいいが、抜け駆けする人間は必ずいる。問題は日本国内だけではなく、全世界でそれをやらなければならず、この理想論は実現不可能となる。2019/11/02
Mc6ρ助
7
自衛権の概念が、1928年のパリ不戦条約以降と知ったことは収穫なのだが、池内先生の不戦を前提とした議論は昭和の香りが強くして、集団的自衛権と自衛権の間で揺れる平成・令和の日本人にはナイーブに過ぎるような気がする。とはいえ、不平等同盟と言ってくれてるのに地位協定の改定を持ち出せない日本の自衛権が何を守るのかアラ還の爺さまにはついて行けるわけもなく、まして、そのことに自覚的でない軍事研究はある意味731部隊などよりも恐ろしいと、所在なく佇むしかない。2019/08/03
ともたか
4
それはデュアルユースであろうとなかろうと軍事研究は 人を殺す、傷つけることが目的になるからだろう。2019/08/03
-

- 電子書籍
- 学園天国(分冊版) 【第49話】 ぶん…
-

- 電子書籍
- &フラワー 2023年43号 &フラワー