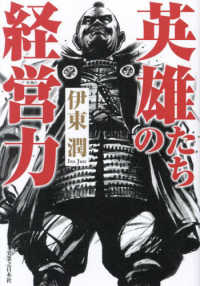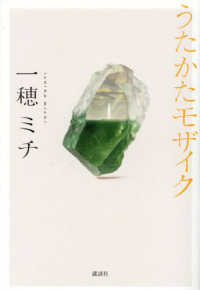内容説明
米軍海兵隊の普天間飛行場の移設をめぐる国と沖縄県の対立は根深い。保守と革新の単純化した構図でとらえられることの多い沖縄問題をどう考えればよいのか。本書では琉球処分、沖縄戦から米国統治、そして日本復帰という近代以降の歴史を踏まえ、特に沖縄県の行政に注目し、経済振興と米軍基地問題という二大課題への取り組みを追う。理想と現実のはざまで苦闘しつつも、リアリズムに徹する沖縄の論理を示す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かごむし
24
ニュースとして入ってくる情報だけをつなぎ合わせても、全体像にはならないということを痛感した。この本は、沖縄県の副知事や、県庁の部長クラスだった人たちで分担して書いたものである。そのため、そもそも論や枠組み論ではなく、非常に実務的であり、官僚的である。法律に基づいて処置しなければいけないことがらについて、県民感情、政治的なものに対しての、現場の葛藤、苦悩のようなものが垣間見えた。沖縄戦で社会的インフラが壊滅し、1972年までアメリカ統治下にあった、基地の島沖縄。観光用パンフレットに載らない沖縄の姿があった。2017/11/04
風に吹かれて
17
中井眞弘多氏が知事を務めていた時期に知事公室長、総務部長、土木建築部長を担っていた人たちを筆者としている本である。沖縄と言えば米軍基地問題がまず頭に浮かぶが、琉球処分や米国統治を経てきた沖縄のもうひとつの大きな課題が経済振興。こういった問題に取り組んできた行政マンが描いた沖縄の行政史である。政治の問題である米軍基地についての考察を目的に本書を読むと肩透かしを食うが、国と沖縄県民の多様な声の間で少しでも“問題”から沖縄を前進させるべく取り組む沖縄行政の取り組みを知ることが出来る。これもひとつの真実だ。2017/05/02
skunk_c
16
仲井真知事のブレーンを務めた歴史学者の高良倉吉他、当時の沖縄県幹部が、行政官僚としてやってきたことを記したもの。普天間基地移設であるとか、跡地利用の問題であるとかを、まさに行政的な手続きを説明しながら、国際条約下の地方行政の限界を示しながら、どう取り組んだかを書いているのだが、やはりどこか「言い訳」に近いものを感じる。原因は著者達が行政官や学者だったとしても、当の知事が政治家(元々は財界人だが)として振る舞っていたからだと思う。辺野古埋め立て許可のあのタイミング、手続き上そうなったというがあまりに絶妙。2017/01/31
すみけん
12
沖縄の基地問題の実態を学んだ上でないと、自分の考えが偏ってしまいそうなので、この種の本、2冊目。お役人の方々も間に挟まれて苦労されていることはわかる。この立場であれば、法に基づき事を処理するしかないなだろう。でも、どこか上から目線で、血が通っていない感じもなくはない。知れば知るほど難しい。でも、あの海を埋め立てて環境保全が保てるのか?ジュゴンはどうなる?有明海の問題から学ぶことはないのか?もう少し、勉強します。2018/01/15
いとう・しんご
11
高良倉吉さんおっかけ。彼は副知事だったそうで、その頃、共に庁議を囲んだ仲間達で執筆している。歴史、復帰後の振興計画、交付金や財源全体(「沖縄県は、「基地」や「補助金」という札束で左右されるような存在ではない」P124)、返還後の軍用地活用の経済効果(那覇新都心で32倍、北谷町桑江・北前地区で108倍P149)、基地返還の努力と普天間埋め立て承認に関する行政事務執行、などハードな話しが続く。僕も行政職員だったので、クールヘッド、ウォームハートで努力してきた県職員の姿に敬意を表したい気持ちになりました。2025/07/28