- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
盆地が暑くなる要因であるフェーン現象の正体や、やませやからっ風、六甲おろしが吹くしくみなどの「地元の常識」と、「金沢市の年間降水量は178.1日」「八月の大阪市の平均気温28.4℃は那覇市よりも高い」といった驚きの数字を網羅。さらに、北海道陸別町で見られるオーロラ、徳島県牟岐(むぎ)大島の千年サンゴ、八代海の不知火(しらぬい)など自然の妙(たえ)なる特殊現象も紹介する。地理と気候の基礎知識を楽しむ文理融合の一冊。日本の地理・気候は面白すぎる! ◎流氷が太平洋にも現われる? ◎秋田美人と気候の関係 ◎なぜ雷は北関東で多く発生する? ◎関東大震災で相模湾に没した駅 ◎軽井沢は日本一霧の多い町? ◎積雪量世界一を記録した地点が滋賀県にある ◎三次盆地に立ち込める幻想的な霧の海 ◎奄美大島はなぜ日本一日照時間が短いのか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
氷柱
7
602作目。7月25日から。特徴があることが特徴的でないという「個性がないことがむしろ個性的」の真逆をいく日本の地形について述べられている。特徴がありすぎて殆ど覚えられないけれど、実際にその土地に住んでみるとこの作品の内容を実感と共に記憶されるのだろう。今回は図書館で借りてしまったが、購入して手元に置いて地図帳と共にのんびり眺めるのに最適な作品だ。この大雨の影響で各地で被害を出している水害の原因もこの作品を読むことで理解できる。同じ日本でもまだまだ知らないことがたくさんあるし、多様性についても驚かされる。2020/07/28
はち
5
知らない土地に出かけると大体風邪を引く。慣れない気候にやられてしまうことが多い。瀬戸内海気候になれてるので、夜になって急激に冷える土地にやられてしまったのだ。そこでこういう本を置いておくと便利。旅行ガイドの参考書にも向いてるし、自分の住んでるところだけ読んでも良いし。文体も平易で、非常に読みやすい。意外なことも多いし。2011/12/08
bittersweet symphony
3
浅井建爾さんは地理・地図をメインに活動しているライター。本書ではそれに絡めて各地の気象・気候の特徴を概説しているということになりますが、この手の雑学系の本にありがちな行政のホームページ(気象庁のデータベースが大活躍)と百科事典、同テーマの他書のつまみ食いで一丁上がり的な内容。地理条件と気象の関係性の大枠の説明という意味では中高生向けレベルだけれども、気象のほうが著者の専門外なのでそちら方面の学習意欲を煽る印象はありません。著者の若い頃の自転車旅行の話があちらこちらに出てくるのは致し方ないところか。2011/10/19
もんしろちょー
3
地元の話がちょっぴり出ていたので気になって読んだ本。天気なんて、空で勝手に日が出たり雨が降ったりしてるイメージが強かったのだけれど、地面の、地形の影響が強いのだということがよくわかった。山すごい。海と風もだけれど。それぞれの地域がそれぞれの気候の難点と恩恵を受け入れて、特産ができたのだなあ。いろんな地域の人たちと話をするのに、いいきっかけになるかもしれないなと思いました。2016/02/04
tkmt
2
広戸風と釧路の霧に関する話が興味深かった。2019/10/11
-
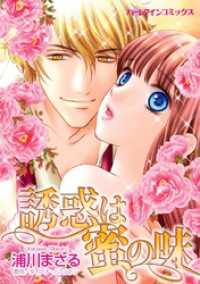
- 電子書籍
- 誘惑は蜜の味【分冊】 9巻 ハーレクイ…
-
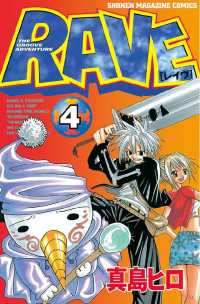
- 電子書籍
- RAVE(4)




