内容説明
植物の常識に照らすと、生態が少し奇妙なイネ。だがそれゆえに、人に深くかかわりその生活や歴史までも動かしてきた。イネとは何か、なぜ人を魅了してやまないのだろう。その秘密にせまる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
36
親類ご近所共同の手植えの情景知る最後(?)の世代としては、後半の文化論は失われしものへの哀惜と読めるけど、米が余り減反始まって一世代、無理はあると思う。そこは差し引いて、イネという作物について一通り学べるプリマ-らしい本でした。2020/09/11
鯖
26
もちは血糖値が早く上がり幸福感を得やすいのでハレの日の食べ物になった。田んぼに水をいれるのは雑草対策になり、水が有害物質や余った栄養素を流すため連作障害が起こらない。ケイ素を含み、ガラスのように硬いせいで、葉の栄養価は低い。稲は花を大家させ、三つの花を統合して、一つの花を作ることで少数の大きな種子を作る。熟しても地面に落ちない非脱粒性をもってしまった突然変異が小麦と稲の元であり、人間の大発展の大恩稲。面白かった。2021/05/19
タルシル📖ヨムノスキー
24
手に取ってみたら、以前読んで面白かった〝たたかう植物〟の著者さんの本でした。この本はイネ(米)を様々な角度から取り上げた新書。まずはお米とはそもそも何なのか、どんな種類があるのか。次にイネを植物学の視点から解説し、水田という栽培法に触れ、日本の歴史とお米の関係。最後は日本文化とお米にまつわるエッセイまで、幅広い内容が収録されています。本筋とはズレるけれど学名がなぜラテン語なのかという話は、目から鱗でした。それから江戸時代の「石(こく)」という単位、「一石はひとりの人間が1年間食べるお米の量」というのも。2023/04/15
こも 旧柏バカ一代
24
そういえば、イネを中心に据えた歴史は読んだ覚えは無かった。連作障害が起こらないプロセスにも納得。水って重要だよな。。2020/07/12
はじめさん
22
2019岡山西大寺ビブリオバトルチャンプ本。イネ、すなわち米。我々日本人にとっては主食たるこの植物の歴史を紐解く。/ イネは動物に食われないように背を伸ばして、成長したらさっさと穂を地面にまいて次世代にDNAを繋ぐよう進化したが、大型畜獣は穂ではなつ茎食えるようにこちらも進化。ある日人間が穂がバラバラ落ちない突然変異種を見つけた。これによって穂(米)を食い始めた。短足のあけぼの。田んぼアートなんかに使われる古代米は赤い。アルビノ化したものを固定して現在の白米に。/ 田んぼは自然ではなく人工物。アグリパンク2019/09/29
-
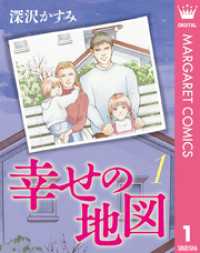
- 電子書籍
- 幸せの地図 1 マーガレットコミックス…
-
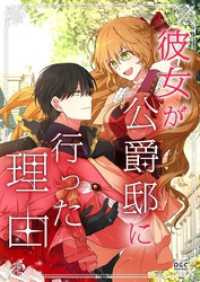
- 電子書籍
- 彼女が公爵邸に行った理由【タテヨミ】第…
-
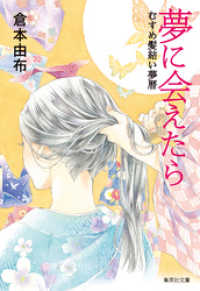
- 電子書籍
- 夢に会えたら むすめ髪結い夢暦 集英社…
-
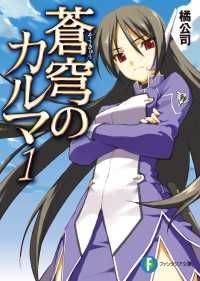
- 電子書籍
- 蒼穹のカルマ1 富士見ファンタジア文庫





