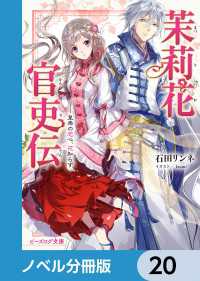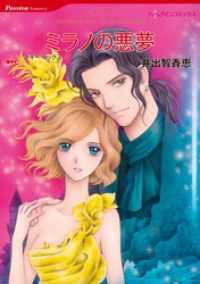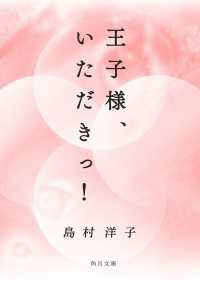内容説明
ポピュリズム、ポストトゥルース、グローバリズムに直面する今こそ読む――“アメリカのデモクラシー”その根源への探究デモクラシーこそは歴史の未来である――誕生間もないアメリカ社会に トクヴィルが見いだしたものは何か。歴史的名著『アメリカのデモクラシー』では何が論じられたのか。「平等化」をキーワードにその思想の今日性を浮き彫りにする、鮮烈な思考。あらゆる権威が後退し混沌の縁に生きる私たちは、いまこそトクヴィルに出会い直さなければならない!いま日本の思想界をリードする著者が、第29回(2007年) サントリー学芸賞(思想・歴史部門)を受賞し、現在に至る地位を築いた好著の文庫化。文庫化にあたり、現在の政治・思想状況をふまえた「補章」を増補。トクヴィルの「今日的意義」は増すばかりである。ある意味で、「トクヴィル的」とでも呼ぶべき状況がますます強まっている―(「補章」より)【本書の主な内容】第一章 青年トクヴィル、アメリカに旅立つ第二章 平等と不平等の理論第三章 トクヴィルの見たアメリカ第四章 「デモクラシー」の自己変革能結び トクヴィルの今日的意義補章 二十一世紀においてトクヴィルを読むために
目次
第一章 青年トクヴィル、アメリカに旅立つ
第二章 平等と不平等の理論
第三章 トクヴィルの見たアメリカ
第四章 「デモクラシー」の自己変革能
結び トクヴィルの今日的意義
補章 二十一世紀においてトクヴィルを読むために
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
40
文庫で200ページという小著で、かなり丁寧に書かれています。しかし、分かり難いと感じるのは、民主主義が我々にとって空気のような存在であり、自意識に触れるようなセンスを必要とするからでしょう。トクヴィルの議論は逆説的で、平等な社会だからこそ不平等の感度か強くなることは読み流されてしまうかも知れません。旧体制側の敗者であるトクヴィルの出自から新たな見方が生まれたというのは、敗者の言葉から新たな想像力が生まれるという点で、自由民権運動の挫折から日本近代文学が生まれたという柄谷行人の議論との重なりを思わせます。2021/04/18
ta_chanko
27
平等化・民主化は時代の流れ。ヨーロッパに残る貴族制と、平等なアメリカ(白人)社会の対比。タウンシップによる自治、政治と宗教の分離、連邦制‥。若きフランス貴族が見たアメリカ社会の特徴。しかし一方で、民主政が衆愚政治や全体主義におちいる危険性も予測。トクヴィルの恐るべき慧眼。2023/03/20
しんすけ
19
最近トクヴィルがよく読まれるようになった。しかしトクヴィルを読んで明確な答えが得られることはほとんど無い。 それでも読まれるのは、トクヴィルに現代の閉塞的混沌状態と重ね合わせることができるからに違いない。 トクヴィルは貴族階級に生を受けた人物であり、フランス革命後に革命派から父母が死刑寸前にまで追い込まれている。 したがってトクヴィルが語るデモクラシーはアリストクラーシーと併用して観察するべきなのだろう。 2019/11/24
TS10
17
アメリカの観察者であると同時に、社会類型としての「デモクラシー」の構想者でもあったトクヴィルのエッセンスを紹介する一冊。母国フランスを意識して理想的社会としてアメリカを称揚する一方、その中にアメリカ的なるものとは異なる、「諸条件の平等」の力学が働くデモクラシー社会をも見出した複雑な思想が語られる。伝統的権威を否定し、自分自身の中にのみ知的権威を認める民主的人間が、逆説的にも彼らと同質な人々が数多承認する意見に権威を求めること等、トクヴィルの分析したデモクラシー社会の欠点は現代にも大きな示唆を与えている。2024/04/18
皆様の「暮らし」を応援サポート
17
トクヴィルは頭の良い人たちに任せて、私は「下水道から這い出してきたような」言葉を信じることにするわね。2021/10/28