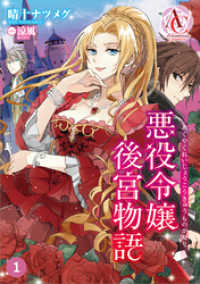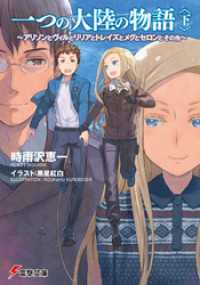- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
125代にわたって続く天皇制。その「天皇」の運用において、最も画期的だったのが「院政」の開始だった「万世一系」とうたわれる血統の再生産は、いかにして維持されてきたのか、それを支えてきた組織や財政の仕組み、社会の構造がどのようなものだったのか。「天皇制」の変遷から、日本の歴史を読み解く。本年4月30日、江戸時代の光格上皇以来、約200年振りに天皇が退位し、「上皇」の名称が復活することになりました。これは憲政史上、および一世一元の制が定められた明治以降初めてのことになります。神話時代は除くとしても、日本の天皇家は少なくとも千数百年にわたって、125代という皇位継承を実現してきました。これが可能だったのは、「天皇」の運用が非常に柔軟だったからでした。天皇不在で皇太子が政務をとった時期もありましたし、女性天皇や幼帝が位につく場合もありました。また天皇は終身の地位ではなく、譲位も頻繁に行われていました。天皇の地位が日本の頂点に置かれていたことは間違いないとしても、時代の政治状況に応じてかなり大きな幅をもって運用することができていたのです。いえむしろその運用のさまは、ほとんど場当たり的といってもよいほどです。その「天皇」の運用において、最も画期的だったのが、おそらく「院政」の開始でした。古代以来の制度である太政官制を保持したまま、速やかな政治的判断と断固たる政治的決断を可能とする回路を作り出し、新しい時代を開いたのが、この院政という方式だったのです。天皇の父であることを根拠に権力を掌握した「院」=上皇のもとに、日本のさまざまな場所で胎動していたエネルギーが引き寄せられ、大きなうねりとなったなり、中世という、新しい時代を開いたのです。本書では、「院政」という政治方式をを通して、「万世一系」とうたわれる血統の再生産がいかにして維持されてきたのか、またそれを支えてきた組織や財政の仕組み、社会の構造がどのようなものであったかを考えていきます。
目次
はじめに
第一章 院政以前――譲位と太上天皇
第二章 摂関政治と後三条天皇
第三章 中世の開始と院政への道
第四章 白河院の時代
第五章 院政の構造
第六章 内乱の時代
第七章 公武政権の並立
第八章 院政と公武関係
第九章 中世後期の皇位継承
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
Toska
さとうしん
bapaksejahtera
MUNEKAZ