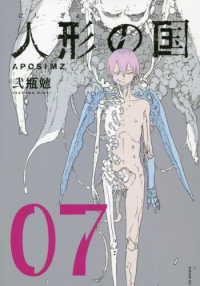内容説明
地球温暖化や資源の枯渇、小惑星や彗星の衝突、太陽の膨張……。地球がいずれ壊滅的なダメージを受けることは避けられず、人類は生き延びるために宇宙に移住する必要がある。
世界的に高名な理論物理学者で、未来学者としても定評のある著者が、宇宙移住への道を3つのステップで解説する。まずは月や火星に入植し、次に太陽系外の星々への進出を果たし、それと当時に人体の改造や能力の強化を行うというプランだ。
NASAやイーロン・マスク、ジェフ・ベゾスらの挑戦や、AIやスターシップなど最新テクノロジーの進展を追いながら、驚くべき人類の未来を見通す。最高にエキサイティングな科学読み物。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜長月🌙
91
太陽系外の惑星の存在が証明されたのはごく最近の1995年です。人類はこれらの惑星に行けるでしょうか?この本は科学的事実による宇宙学の最先端を紹介してくれます。別の惑星に行く意義の一つに人類のバックアッププランがあります。人類がもし核戦争や食糧枯渇、温暖化などで滅亡しても「2つの惑星の住人」であれば救われます。が、そのためのゴルディロックス(イギリス民話3匹のくまより)の惑星を見つけても遠すぎるかもしれません。「AQUA(天野こずえ)」 のように火星の氷でテラフォーミングするのが手近な方法かもしれません。 2020/01/26
夜長月🌙
76
(読書会のための再読)太陽系外に惑星があることが証明されたのは驚くことに1995年です。この功績に対して2019年にノーベル賞が贈られました。今では研究が進み4,000個以上の惑星が見つかっています。恒星と違い惑星は光りませんから光学的には見つけられません。2つの方法があり、トランジット法は恒星の前を惑星が横切ると光度が下がることを利用しドップラー法は恒星と巨大惑星がお互いの周りを廻っている時、恒星が前後運動して見えることによります。有名なドレイクの式によると生命体のいる惑星は200億個以上と言われます。2020/03/22
みき
51
実に面白い。人類が宇宙に行く、居住するにあたって現在の科学はどこまで進んでいるのか、そして何が足りないのかをディスカバリーチャンネルの司会を勤めていた著者が語ってくれる。著者がひも理論の第一人者のため多少の偏りがあるのは仕方ないがそれでも非常に読んでいて未来の科学への期待に胸が膨らんでしまう。個人的には宇宙の終焉についてのビッグクランチ、ビッグフリーズに対してビッグリップという考え方があることに驚き、個人的にはこっちの方が理論的な整合性はありそうに感じた。それにしても、宇宙……行ってみたいなぁ……2024/06/02
ワッピー
27
オンライン読書会SBC推薦本。宇宙開発を軸とした人類の未来を考察する科学読み物。普段なら敬遠しがちな学術書でしたが、手に取ってみると科学技術の進歩はイマジネーションに基づいており、しばしばSF作家のビジョンが未来を予言していたことも示されていて、引き込まれました。『Ad astra』のスタートラインは大気圏脱出のためのロケット技術であり、太陽系内の資源を有効活用するための星の理解、そして労働力(あるいはアバター)としてのロボット技術、ようやく太陽系を出る恒星間宇宙船と人間のライフサイクルの問題、(↓)2020/03/31
ばんだねいっぺい
27
NASAは、銀河鉄道を作る構想っぽい。行き帰りの手段はともかくとして、「住む」にあたってのハードル「テラ・フォーミングと人間の身体的宇宙適応」が自分にはどうも厳しそうに思えた。でもでも、夢物語ではなくなってきてるという感じは、伝わってきた。やがて、お盆は地球(テラ)へ里帰りかもしれない。2019/08/20
-

- 電子書籍
- 千夜千食物語 ~敗国の姫ですが氷の皇子…