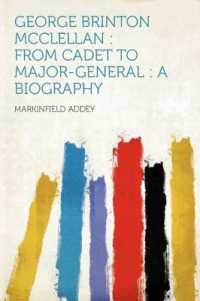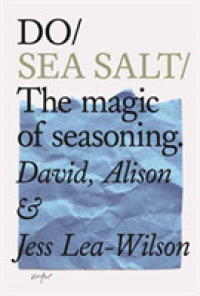内容説明
「博打好き」の中国資本によるラオスの都市開発から、格差最小富裕国ルクセンブルクの歴史的叡智まで――
世界105カ国をわたり歩いてきた著者が描き出す、各国の地政学的ダイナミズム!
・高架上の遊歩道「ハイライン」にみるNYの都市再生
・平和の配当に潜む毒饅頭、東ティモール
・テロの爪痕の残る国際リゾート地ニースを脅かす排外気分
・高級モールとスラム以下の生活が混在する南米アスンシオン
・バルカンの火薬庫、歴史に見る戦争と平和の分かれ道とは? …etc
大好評『世界まちかど地政学』の第2弾。
日本の未来を照射する世界経済のリアルがここに。
目次
第1章 成長目指す貧困国 平和の配当に潜む毒饅頭
第2章 ニューヨーク・再生と格差拡大の現場
第3章 バルカンの火薬庫はいま:旧ユーゴとアルバニア
第4章 極小の公国から見える欧州の本質
第5章 レバノンとヨルダン・戦地真横でのかりそめの安寧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
57
世界105カ国に旅し、行ってみてから考える、という著者のスタンスがとても面白い。今回17カ国17都市が取り上げられているが、このなかで行ってみたい場所は、ニューヨーク・ハイライン・トランスポーテーションハブ、ラオス・ビエンチャン、ヨルダン・アンマン、レバノン・ベイルート、アルバニア・ティラナかな。海外の国を知ると、日本は「水が豊かな国」だということがよくわかる。それが日本文化に反映されているのではないか。藻谷さんは50歳を越えて旅もしんどくなってきたと言うが、海外のレポートをこれからも発信していって欲しい2019/07/16
たまご
24
世界100か国以上訪問している作者の,各国首都数時間滞在弾丸ツアー的工程からでも情勢を分析できる力にすごいなーと.そして,旧ユーゴの民族・宗教対立などの解説のわかりやすさ,いろいろな国を日本の都市,日本の距離で置き換えるわかりやすさ(時にわかりにくさ?)にも感嘆. 海外に行くときにできるだけその国の本を読んでから,と思って何故かバリに行く前に東ティモールの本を読んだ私には,取り上げられてて親近感を.料理がおいしそうだ.そしてヨルダンにも今の国王の間に行ってみたい…2020/03/21
奈良 楓
20
【◎】第一弾が面白かったので即買いした本。街歩きから見えてくるその国の市井の模様に、歴史事情等をまじえた地政学講座第二弾。あいかわらずきれっきれの洞察を見せてくれます。個人的には、もめにもめた旧ユーゴの国々と、レバノン・ヨルダンが印象深い。2019/08/04
月をみるもの
14
昔々、外国の地理と歴史を手軽に勉強するのに一番良い教科書が「地球の歩き方」というガイドブックだった頃を思い出す。最近海外に出かけるのがすっかり億劫になりつつある自分を、叱咤されたような気になった。2019/12/14
Sakie
13
藻谷さん相変わらずせわしない。Googleマップを駆使して追う私もへとへとである。この世界はどのように出来上がっているのか。重要なのは『何が「あるか」よりも、普通ならあるはずの何が「ないか」を探す観察力』と位置づけて世界を巡る。まさに百国百様、しかし違った中にも『同じ構造が繰り返し現れる』瞬間を追体験する。国内に産業が無いのに消費を煽る資本主義がねじ込まれている貧困国。歴史的条件と戦略の上に奇跡的な立ち位置を確立した小国。国体を維持することは、歴史の偶然と積み重ねのうえの奇跡を、智で先へ繋ぐ努力と見たり。2023/08/23
-
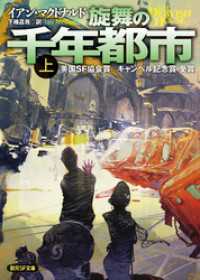
- 電子書籍
- 旋舞の千年都市 上 創元SF文庫