内容説明
王の法より仏の道──。
天平13年(741年)3月、聖武天皇に招かれ、謁見する僧侶がいた。僧の名は、行基。民草を救うため、仏の教えを広めた僧は、その人心への影響力から、朝廷に恐れられ、弾圧すらされた。朝廷から大僧正の位を授けられ、文殊菩薩の化身とよばれた男はどのような生涯を送ったのか──。自然と愛するものに囲まれ、仏の道に目覚める幼年期から東大寺大仏建立、入寂までを丹念に描いた、長篇歴史小説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あさひ@WAKABA NO MIDORI TO...
128
たまには、こういうちょっと真面目チックな本も良い。自分第一、自分が自分がと、狭い視点で世の中を見ているとき、「民のために尽くせ」なんて、頭をガツンと殴られたような衝撃とともに、そんな自分がちょっと恥ずかしくもなる。仏教には特段関心もない自分でも、さらさらと透き通るような清水で心を洗われたような感動を覚えた。失いかけているのかもしれないが、それは人としての一つのあるべき姿なのだと思いたい。2020/09/14
タイ子
57
空海、親鸞などの高僧は知っていても、行基の人となりは知識不足ながら今作で初めて知ることができた。奈良時代に生きた人徳を兼備した高僧行基。とにかく民の為に生涯を尽くして最後に聖武天皇とともに東大寺建立に携わるが、惜しくも行基が入寂して3年後に開眼供養が行われた。日本全国に49の院を建て、池沼橋の造築に心身をくだくも出る杭は打たれるで朝廷から弾圧を受ける事も。当時のややこしい人名や地名を教科書でなく物語で読むとこうもすんなり入るものかと読書の妙を改めて感じた。ちなみにこの50年後に空海が現れる。2019/06/27
trazom
29
私たち奈良県人は、この人のことを、親しみを込めて「行基さん」と呼ぶ。何よりも民のことを思う深いご慈悲に満ちた行基さんの足跡が、時代背景とともに見通しよく綴られている。行基さんの一生の中には、僧尼令違反者としての朝廷からの弾圧、行基集団内での規律の乱れ、一転して大僧正に就任したことに対する転向批判、聖武天皇と光明皇后の狭間での苦悩など、数多くのドラマと葛藤があったはずだ。しかし、この小説は、あえて悪人を描かず、温かな雰囲気に終始しているが、それは、文殊菩薩の生れ変りと称された行基さんのお人柄そのものである。2019/05/30
ひさしぶり
23
霊場巡りの始めの頃は行基さん、役行者、元三大師、びんずるさんの区別がつかなかったw。宗教雑誌に連載されて目にとまる。御伽話風ですが史実に基づいてます。東大寺大仏建立に超尽力したのに開眼に間に合わなかった残念な人。役行者小角は優婆塞で、行基は入唐し玄奘三蔵に学んだ道昭のもと剃髪、役行者のもと荒行、徳光に受戒で比丘。役行者が麒麟に憧れていたとか、蜂子皇子や前鬼・後鬼、喜光寺のこと色々学べれました。行基さんゆかりの寺やお墓を回ってみたくなりました。2024/06/17
ソングライン
17
行基開湯という言葉を見聞きする度に、個人的に何故多くの湯を開くことになったのかと疑問に思っていた奈良時代の高僧行基。彼は大化の改新の中大兄皇子が天智天皇となった668年に生まれ、81歳で亡くなるまで一貫として衆生救済を実行します。僧となるための修行の後、49もの院と諸寺を建立し、報われることなく亡くなっていく人々の救済のため、治水、架橋、休息所などの建設に献身します。小説内では書かれてはいませんが、その過程で温泉を見つけたのだと思います。誰かのために生きる大切さを改めて教えてくれる伝記小説です。2020/06/29
-
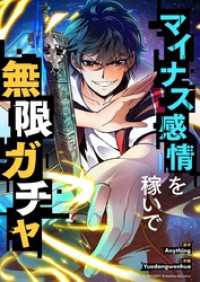
- 電子書籍
- マイナス感情を稼いで無限ガチャ【タテヨ…
-
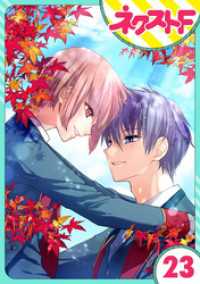
- 電子書籍
- 【単話売】幕末ファミリア 23話 ネク…
-

- 電子書籍
- 推しネコ ~推しのネコとして飼われるこ…
-
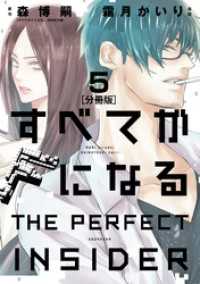
- 電子書籍
- すべてがFになる -THE PERFE…





