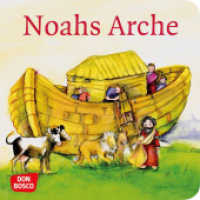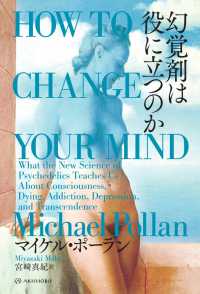内容説明
言葉は人々の暮らしや文化を映し出す鏡。普段何気なく使っていても、じつはそこには数々の複雑な歴史や秘密が隠されている。日本語の成り立ちや仕組みを知り、美しく使いこなすための技をやさしく学ぼう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
べる
12
言葉は時代の変化に結びつき暮らしを映し出す。四世紀頃、百済の渡来人から漢字を学び、文字で言葉を記録することを知り貴族や知識階級の人が学び始めたこと。平安時代に平仮名やカタカナが生まれた経緯や仮名を全部一度ずつ使った作品が様々に作られたこと。鎌倉時代は文化の担い手の中心が僧侶や武士に移り仏教を布教するために平易な文章が一般大衆に広がったり、武家風の力強さに満ちた言葉遣いが発達したこと。室町時代に足利氏をはじめ関東の武家が京都に住み、都と地方の入り混じった文化が生まれ現代日本語の源流になったこと。学び多き書。2025/04/16
ドラマチックガス
10
日本語の文法や発音などの歴史をわかりやすくまとめた本。面白い。だけど、知りたかったいくつかについてはよくわからなかった。1つ。平安時代の人たちは古文のように話していた? かつては口語と文語が完全に分離していたから、源氏物語のような話し方をしていたわけではないと聞いていたけれど、この本によると口語と文語がわかれたのは江戸あたりとか。平安人は「いとおかし」とか言っていた? 1つ。かつては方言がはっきりしており隣村とも言葉が通じなった。これも、方言がはっきりしたのは藩の力が強まったため、と。類書を読むか。2023/11/25
Chicken Book
6
すごく読みやすかったし、内容もわかりやすくて面白い。2021/09/03
乱読家 護る会支持!
6
古代から現代までの日本語の変遷。 中国との交流時期により発音が異なる漢字。 平安時代に漢字を元に造られたひらがな(安→あ、畿→き、計→け、武→む 等)。整備された動詞・形容詞の活用形。室町時代に整備された尊敬、謙譲、丁寧語。 江戸期に多様化、活用形なと文法が複雑化。標準語を作った明治政府。。。 言語は常に変化している。あと100年もしたら方言はなくなるのでしょくね。で、その前に「知らんけど」を日本中に普及させよう!知らんけど(笑)2019/09/11
manabukimoto
3
漢字の伝来から始まり現代まで日本語の通史。 面白かったのが鎌倉時代。平安時代から始まった「仮名」遣いが広まる。でも「漢字は男らしく、仮名は女らしい」という馬鹿なジェンダー意識が1000年前にも存在し、「かへりごと→返事(へんじ)」という語に。確かに、中国語には「返事」という語は無く、「和語由来の音読み」という歪んだ漢字至上主義熟語が誕生したらしい。 現代における諺の意味の変化にも。「情けは人のためならず」という自己利益中心主義の諺も、「親切のしすぎは相手のためにもならないよ」と。良き変化である。2023/10/04
-

- 電子書籍
- なかなか稀少な光谷さん【分冊版】 13…
-

- 電子書籍
- 腐肉列車【タテヨミ】58 Ruby R…