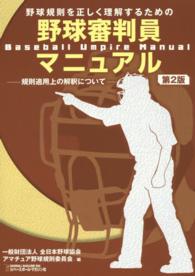- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
ペイペイ、LINEペイ、NTTドコモ、楽天、アマゾン……政府の旗振りの下で吹き荒れる、キャッシュレスの大嵐。IT・金融各社がしのぎを削り、米中巨大資本も虎視眈々と狙う、日本の300兆円消費市場を誰が制するのか? フィンテックがもたらす「信用格差社会」をいかに生き抜けばよいか? 激動の業界と私たちの暮らしの行方を、30年の取材をもとに第一人者のジャーナリストが読み解く。
序 章 ドキュメント「ペイペイ祭り」
第1章 現金の壁を突破せよ!―キャッシュレス狂騒曲
第2章 キャッシュレス社会はアメリカで始まった
第3章 キャッシュレス先進国に躍り出た中国
第4章 「信用スコア」の衝撃
第5章 GAFAがすべてを支配する―狙われる個人情報
終 章 データ監視社会で身を守る
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
44
自分の情報は、自分で守る。この新しい時代の訪れを予感させるのが、政府が「情報銀行」と呼ぶ管理機関だ。この情報銀行は、日本再興戦略2016での提言に端を発し、2016年12月に施行された官民データ活用推進基本法に基づいて構想されているもの。個人の購買履歴、家計収支、健康情報といった多様なデータを一元的に管理し、個人の意向に合わせて、情報を必要とする企業への提供を仲介するビジネスを行う。GAFAMに代表される企業に握られてきた個人情報の利活用に、利用者も主体的に関わることを可能にする画期的なアイデアと言える。2019/03/26
kawa
39
日常的電子マネー&カード決済派なのでキャッシュレスと言っても?の思い、あの「ペイペイ」狂騒劇に興味を持っての本書。その点については大した内容ではないかもなのだが、キャッシュレス社会のアメリカや、そこに先進国として躍り出た中国等、為政者による個人の情報管理の状況にはゾワァと寒気を感ずる内容。ある意味「警鐘」の書なので、更なる個人情報を守る方策を期待したいところ。パソコン・スマフォを持たないアナログ派が時代の最先端への皮肉的展開も有り得る。それはそれで愉快だが、メーターが利用できなくなると葛藤するだろうな。2019/02/27
大阪魂
37
まだまだ現金持ち歩きまくってるんやけど、いろんなところで〇〇payってやってるから、キャッシュレスの世界、いまどんななってるんか勉強しよっておもて読んでみた!QRコード決済とか、ほんま便利になってきてるんやねー!キャッシュレス先進国・中国はクレジットカード作れるほど「信頼」がなかったからデビットの銀聯カードがでて、スマホの普及で一気にキャッシュレスが進んだとか目からうろこやった!韓国のキャッシュレスも政府誘導で85%!でもその分、情報が国とかGAFAに筒抜け、評価社会になってきてるんやね…勉強なったわあ…2019/08/09
hk
25
「ペイペイ祭り」を掴みにキャッシュレス決済の現状と課題を紹介している。アメリカで芽吹いたクレカ文化が、金融インフラが未整備だった中国にて敷衍されて急速に普及。それが足元、大波となって日本を飲み込もうとしている。 …決済手数料が割安。現金管理コストを浮かせられる。政府は徴税が容易に。消費者は現金を持つ煩わしさから解放。… 利便性は確かに多いが「個人情報が何者かのもとで一元化されてしまう」という懸念が付き纏う。QR決済を使わなければならないという空気には、何者かの悪巧みがあると穿ってしまうのは私だけだろうか。2019/04/28
C-biscuit
18
図書館で借りる。キャッシュレス覇権ということで、PayPayやメルペイ、d払いなどの各社のシェア争いの話が中心とも思われるが、内容はセキュリティや個人の信用、プライバシーにまで及ぶ。よく分析されたが内容と感じる。日本にいると現金で不自由しないが、海外ではもやはキャッシュレス決済が標準のようである。日本の中途半端な経済規模と島国が原因とも感じる。キャッシュレスの次に来るであろう個人の信用度についてもすでにスタートしており、それなりにSNSの連携や関わり方で、身近に感じる場面も増えた。将来的には不安も多い。2019/09/23
-
![JOUR 2025年9月号[雑誌] ジュールコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2201988.jpg)
- 電子書籍
- JOUR 2025年9月号[雑誌] ジ…