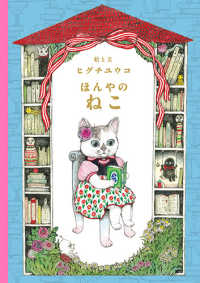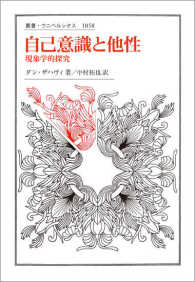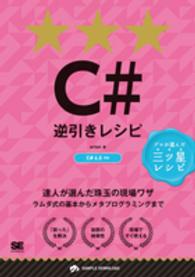内容説明
1944年の解放から,「栄光の30年」,五月危機,石油危機,「ミッテランの実験」の挫折,新自由主義,そしてマクロン政権成立──フランスの戦後を通観すると,そこには「分裂と統合の弁証法」というダイナミックなメカニズムがみえてくる.欧州統合の動きにも着目しながら現代フランスの歩みをとらえる通史.
目次
目 次
序 章 分裂と統合の弁証法
1 「モデル」から「先行者」へ
2 分裂と統合の弁証法
3 相対的後進国
第一章 解放と復興──一九四〇年代
1 解放、対立、和解
2 経済復興
3 第四共和政の成立
第二章 統合欧州の盟主をめざして──一九五〇年代
1 脱植民地化と欧州統合
2 復興から成長へ
3 第五共和政の成立
第三章 近代化の光と影──一九六〇年代
1 「栄光の三〇年」
2 近代化のなかで
3 五月危機
第四章 戦後史の転換点──一九七〇年代
1 過渡期としてのポンピドー政権
2 「栄光の三〇年」の終焉
3 分裂する社会
第五章 左翼政権の実験と挫折──一九八〇年代
1 ミッテランの実験
2 新しい社会問題
3 異議申立ての諸相
第六章 停滞、動揺、模索──一九九〇年代
1 争点化する欧州統合
2 動揺する社会
3 模索する政治
第七章 過去との断絶?──二〇〇〇年代
1 「古いフランス」と「新しいフランス」
2 グローバル化
3 ポピュリズム
終 章 その先へ
あとがき
重要語
年 表
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
32
第2次大戦後の70年のフランスの歴史をコンパクトに記述したもの。著者のあとがきにもあるように、キーワードは一種の「外圧」である「欧州統合」と「移民」。前者は宿敵ドイツを御し、東西対立の中でヨーロッパの平和維持を願う小国(ベルギーなど)の思惑の中で、まさにリーダーとしてそれを実現していく(その点ドゴールは適任だったのかもしれない)前半部と、経済統合が新自由主義的な緊縮財政を指向するのに対し、国内の高い失業率との相克が問題となっていく後半部で異なる様相を見せている。まさに右往左往しながら乗り切っている感じ。2019/01/20
meg
28
興味深い。移民史というか。フランスの歴史と昔と今にまつわるエッセイなんかもあれば読みたい。2025/08/19
たばかるB
26
さらっと触れるつもりが内容満載で肌が破けそう。さておき本書は政治対立を軸に10年区切りでフランス現代史を解釈する。-60までは労働者対経営者の冷戦中ならではの構造。経済が発展しその波に乗れたか否かで中間層は分裂する。70年代オイルショック•ニクソンショックで経済が止まると移民労働者問題が表面化する。政治対立は国民対非国民の構図になった。フランスでは国籍は出生地をベースにするので移民2世3世などがフランス国民になれる。そのため対立の場はがっちりしっかりと国会に持ちこまれるようだ。 2020/08/26
kayak-gohan
19
本書でフランス現代史として、第二次大戦時におけるナチス・ドイツによる占領からの解放から2017年のマクロン大統領(現職)就任までが記述される。本書の構成としてユニークなのは、通史に入る前にフランス社会の発展法則が仮説として提示され、通史が語られる過程でその仮説が検証されていること。その仮説とは「分裂と統合の弁証法」で、具体的にはフランス社会は国民の分裂と統合を繰り返しながら螺旋階段状に進化している、というものである。2021/04/10
bapaksejahtera
18
フランスの政治状況を戦後から数年前迄辿り、政治的対立の叙述を通じて仏社会の特性を知らしめる本。サルコジ退陣とマクロン登場迄述べる点で、何とか現代性を保っている。英国の工業力や独の軍事に比べ相対的に後進性を示した同国が、植民地をテコに開発を図り、それ故に今日マグレブ等の移民増加による様々な社会的混乱を来す。従来の社会上層下層の対立に加え、移民の扱いを巡る政治的対立が生ずる。変則的な大統領制の成立ちやヴィシー政権への清算の遅れも興味深い。但し嘗てモスクワの長女と称された仏共産党の消長について記述が弱いのが残念2024/07/06
-

- 電子書籍
- イタリア人の女の子が居候することになっ…