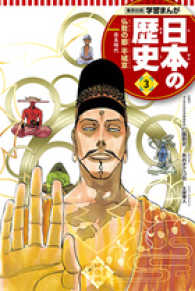内容説明
半世紀前、国王に送った一通の手紙によりイランに留学、日本のペルシア文学研究を大きく進展させてきた女性研究者が、言葉の国イランの、当時と今、その文化の魅力を語る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Maumim
3
著者がイランと出会ったのは26歳、教師として勤務していた頃。そこから、ペルシア語を学び、留学もして、ペルシア語の研究者になっていく。今と違って、海外へ出ることもその情報を得ることも容易くはない。成し遂げたのはまさに人との出会いと、ペルシア語への深い好奇心、と運、だと思う。言語を身につけるのに必要な並々ならぬ努力、があったはずなのに、トントン拍子に進んでいったかのように綴られる。イランの諫言や風習なども収められているけれど、個人的な経歴を綴る「イランと私」が最もおもしろい。2024/04/14
Shigeo Torii
3
郷に入れば、郷に従え、ということか。でも、パイオニアには、敬服!チクリも良いね!2019/09/29
丘の十人
3
イラン革命前、パーレビ王朝時代に、まだ、西側と関係が深かったとはいえ、単身イランに留学したというだけでも尊敬に値する。この時代のかの国の生活、しきたり、2017年に再度訪問した際の様子、副題、「世界一お喋り上手な人たち」の様子がよくわかる。「お世辞でないお喋りは結構なスキル」とのこと。この地域では必要不可欠なのかな。詩の朗読の意味も少しわかったような気がする。2019/06/29
BookaBoo
3
読書の良いところを改めて認識する。人間ひとりが興味のあること全てを体験するのは不可能だが、こうして疑似体験は可能である。ここに描かれているイラン、ペルシア像もほんの一握り中のさらに一握りに違いないが、何を考え、何を大切にしているか知ることができると俄然親近感がわく。現在のイランの政治や核開発まわりのことも絡めて触れてくれたらより面白かったと思うのだが。2019/06/26
さりー
2
最近ペルシャ人留学生の友人ができたので、イランに興味を持ち読了。 彼がいつもペルシアでは〜と言って誇り高い人種なんだなと思っていたが、本書を読み理解が進んだ。ちなみにその彼も日本にハーフェズの詩集を持ってきており、本当にペルシア語を大切にしているんだなと思っていた。 異国に住んで勉学に励むという意味でも、希望を持たせてくれた著作だと思う。2020/06/07
-

- 電子書籍
- 外道坊&マーダーライセンス牙 4