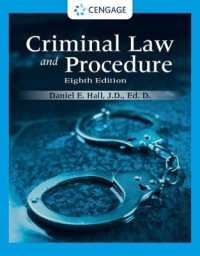- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
協力関係があるところには、必ず裏切り者が生まれます。生物における協力関係についても同じです。1個体、1細胞でも裏切り者が現れれば、協力関係に致命的な影響を及ぼします。生物界における裏切り者とは、他の生物からの協力にただ乗りをするものたちのことです。多細胞生物でいえば、がん細胞のように勝手に増殖する身勝手な細胞のことです。協力関係を長期間維持している生物は、実に様々な方法で裏切り者を抑え込んでいます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あちゃくん
51
血縁がなくても協力しあえるのが人間という生物の特徴と捉えれば、周りの人たちに少し優しくなれる気がした。2021/06/17
ホークス
34
2019年刊。①細胞は4種の分子(DNA、RNA、タンパク質、脂質)を必ず持つ。生物誕生仮説には、DNAの遺伝機能とタンパク質の触媒機能を代行できるRNA祖先説、タンパク質生物や脂質生物が先駆け説など。②真核単細胞生物は細菌を取り込んでミトコンドリア等にする過程で細胞壁を捨て、細胞内骨格(繊維状タンパク質)を得て大型に。DNAもリッチになり機能も高度化。多細胞生物への道が開けた。③生物は単純な裏切り関係が基本。複雑な協力関係はほぼ失敗するが、一部はブレークスルーに成功する。例えば人間。もちろん万能ではない2024/08/27
まいこ
25
進化というと複雑さを増して多機能になるようなイメージを持ってしまうけど、多様性があり自然選択が働くとき、実際は単純な方向に進むという。短期間でたくさん増殖するような細菌が最も個体数が多い。ごくまれに協力し合う性質から複雑な方向に進化するものが現れ、それが真核生物→多細胞→ヒトや膜翅目のような社会的分業 へと、複雑になる方向にアクセルを踏んできた。協力を是とし公平を好みチーターを罰したい気持ちは、ヒトが協力を成功体験として持ち、団体戦で生き残ってきた遺伝的な記憶のようなもの故かもしれないと思った。2023/11/26
那由田 忠
20
とてもおもしろいのだけど、前半に比して後半にもっと具体的な話があるかと思ったらそうでもなかったのでそこが少し残念ではあった。複雑化する進化をとげるものが偶然でわずかしか存在しない、という仮説はそう考えるしかないのだろう。ただ、ホモサピエンスについて考えると様々な種が結果として一種に収斂したわけで、そのあたりに何か別な説明が必要に思った。ぜひ一読してほしい本である。2022/11/03
hisa_NAO
11
生命進化を「協力」を切り口として読み解く。 「生命とは協力の産物」であり「生命はその誕生から現在に至るまで、一貫してもともとは別々の分子や生物が協力関係を結ぶことにより進化して来ました。」 1.分子間協力->2.細菌の協力->3.真核細胞の協力->4.血縁多細胞生物の協力->5.血縁のない多細胞生物の協力。 「生物の進化を理解するといいことは、人生のたいていの悩みはどうでもいいことだと思えるようになること」と言う著者。一種ナイーブな世界観とも思えますが、知ることの目的って、案外それかもしれないなー。2019/08/04
-

- 電子書籍
- 海鳥と狼【タテヨミ】30話
-

- 電子書籍
- クリスマス・キャロル