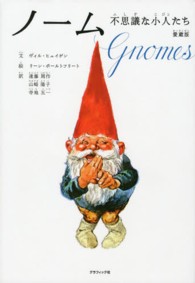- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
なぜ生物は、多様な形をしているのか? その一方で、ペガサスやキングギドラのような、通常の形から逸脱した「怪物」は、なぜ現実には存在しないのか? その謎を解く鍵はゲノムにある。現代科学の最もホットな分野の1つである進化発生学の世界を、最先端の研究者がわかりやすく解説する。生物進化のメカニズムがわかる!!
目次
第1章 原型論的形態学の限界
第2章 形態学的相同性
第3章 分類体系をなぞる胚
第4章 進化を繰り返す胚
第5章 反復を超えて
第6章 進化するボディプラン:アロモルフォーゼ
終章 試論と展望
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
那由田 忠
22
難解な本。比較形態学や進化思想史の、それなりの知識がないとわからない話ばかり。私の理解は以下。ゲノムの偶然の小さな変化が積もっても大分類を変える進化は生まれない。左右相称動物が神経系などで相同の構成を持つのは、ゲノムの内容発現において、神経系や内蔵などの身体の各要素がモジュールとして発現するからだ。ゲノム重合が何度か起こる中で、発生過程で分化が早まることが起こるとボディプランを変える可能性が生まれ、モジュールとして身体要素が互いに安定化すれば新しいボディプランができあがる、という進化過程を提案する。2022/11/19
bapaksejahtera
8
ゲノム遺伝学以前の生物学習者には、受精卵からの胚の変容は、進化を再現する如く不思議に思う迄であった。本書ではこれが意味する/しない所を説く事から開始、ゲノムとその機作につき最新の知見を述べつつ、脊椎動物を始めとする30の動物門の分化が、カンブリア紀に爆発的に発生した理由とその態様を推測する構成。遺伝子が個別ではなく輻輳的なモジュールとして機能した結果、動物門毎に体内器官と機能をボディプランというべき固有の物を構成する。このレベルの進化は個別の小さな変異の積み重ねで起こったのではない由。難解だが啓発的だった2021/02/27
武井 康則
7
門外漢で恥を承知でまとめると、なぜ生物が多様な進化をしたか。環境の急激な変化等もあったが、ゲノムに対応するものが前もってあり、その発現でないかということか。確かに我々人類も飢餓やペストで全滅の可能性もあったが、耐性の強いDNAを持つ者が生き延びたわけで、それが生物全般に適応してもおかしくない。ボディプランとか、新しく刺激的な考えがあったが、何分全くの畑違いで大きな読み間違いをしているのだろう。ごめんなさい。2019/05/27
S
4
動物のボディプラン進化。前半では18-19世紀の学者の出した概念や歴史的位置づけをまとめ、後半は反復説にかわる「アルシャラクシス理論」を説明、進化発生学・解剖学的な観察からその妥当性を議論し、最後はそれを可能とする遺伝子的(モジュール化された転写ネットワーク、カナライゼーション、etc)のメカニズムの試論。それぞれ、知識の裏付けにもとづいてよく考えられていて、とても面白かった。2019/08/03
たか
4
けっこう難しい…2019/07/16
-
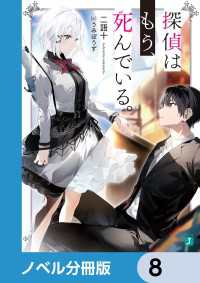
- 電子書籍
- 探偵はもう、死んでいる。【ノベル分冊版…
-

- 電子書籍
- ちくま 2017年12月号(No.56…