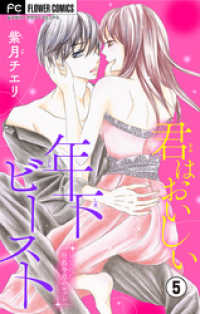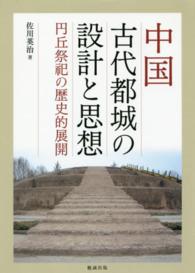内容説明
幕藩体制下に弾圧されたキリシタンは、明治政府によって解放された――。このように思われている「日本社会の近代化」は、歴史の真実なのだろうか。そもそも、「キリシタン」とは何なのか。非キリシタンであったにもかかわらず、領主の苛政に一揆を起こした民衆を「切支丹」として弾圧した事例や、問題化を避けるために、穏健なキリシタン百姓を黙認した事例などを取り上げ、歴史と宗教のかかわりに新しい視野を提供する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かおりんご
29
とても学術的だったので、端折って読んだ部分もあるけれど、総じて勉強になりました。潜伏キリシタン探しに、そんなに躍起になっていなかった時期があったなんて知りませんでした。確かに、狩りまくっていたら、農民がいなくなってしまって、納税されなくなるものね。だったら、異宗として穏便に対処した方がいいわけで。なるほどと考えさせられました。2019/06/06
かんがく
15
江戸時代にキリスト教が禁止されたことは有名であるが、本作では「切支丹」として弾圧された人々が、キリスト教徒のみでなく、仏教などの異端も含まれたことを指摘。近世期の宗教と民衆統制について新たな像が形成されていて面白い。2019/12/20
しゅん
12
江戸期のキリシタン禁制時代には明治以降の世界よりも信仰の自由があったのではないか?という問い。信者には「キリシタン」以外にも(他の人々と同じように)「村人」「農民」「漁民」といった属性があり、そうしたいくつかの所属の中で信仰が曖昧に守られてきた可能性を指摘する。2020/08/15
moonanddai
10
サブタイトルにあるように「禁教政策」と、そこで取締りの対象となった民衆の宗教活動といった内容と言えるのでしょう。「潜伏キリシタン」がどのような信仰を行っていたかというより、どのように潜伏し得たか、に論点の中心があります。潜伏キリシタンは村落共同体の中での共生を選んだがゆえに(キリシタンとは見られても)処罰の対象とはならず、共同体の支障となる「異教・異宗」(真宗や日蓮宗のある一派など)は取締られる。ただ共同体に埋もれる道を選んだことに信仰上の高い・低いはないことに留意しなければならないのでしょう。(続)2020/05/22
nkmr
7
禁教から何十年が経つと、切支丹に関わること自体を皆が恐れすぎて、このままでは何が切支丹で何が切支丹で無いかすらわからなくなりますよ、と荻生徂徠が徳川吉宗に直言している。 ”伴天連の妖術じゃ”って言葉の響きがなんか面白くて好きだったが、どうしてそんなイメージになってったかが理解できた。江戸時代なんて、切支丹の疑いかかる→即踏み絵→即磔というイメージだったが、地域によっては緩やかに切支丹と非切支丹が同じ村で共存していたところもあった、といった辺りも面白かった。2023/04/15