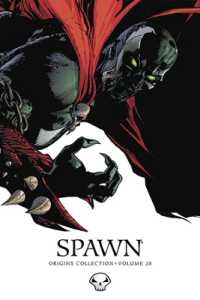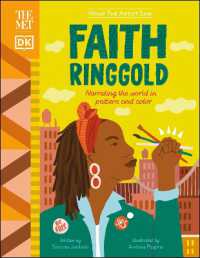- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
伸びる企業・廃れる企業の違いはどこにある? 合併・統合・再編をつづける企業閥の因縁とは?
日本の財閥の中から15を選択。創業者の生い立ちから、中興の祖の知られざる逸話をはじめ、各財閥の現在までの変遷をコンパクトにまとめる。サラリーマンの営業ツールとして、また就活生にも役立つ1 冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
54
「あとがき」にもあるように、江戸時代から現代に至る財閥(あるいはそれに準ずるもの)についての資料的なまとめだ。したがって事実の羅列が続く印象で、読み物そのものとしての面白さより、その関係性などの事実そのものの面白さを感じるかどうかが重要。その意味で僕にとってはかなり面白い本だった。系図や会社のつながりの図が、数ページにまたがっているのは少々見にくい(少し値上がりしても折り込みにしてほしかった)が、意外な人脈もみられる。いわゆる陰謀論的なものは一切なく、とにかく淡々とした筆致。手元に1冊あると便利だ。2020/02/09
Kentaro
44
世間では、三井・三菱・住友の三大財閥を「人の三井」「組織の三菱」「結束の住友」といって比較することが多い。三菱財閥の中興の祖・岩崎小弥太は、社員の個人プレーを好まず、あくまで三菱の「組織人」として動くことを要求していた。 三菱・住友財閥は製造業中心だったこともあり、年功序列・チームプレーを重視し、均質的に優秀な社員を揃えるため、教育・研修に熱心だった。これに対し、金融・商業中心の三井財閥は、個人の資質・創造性を重視し、「教育」よりも「抜擢」を得意とした。2020/01/10
月をみるもの
15
毎日日経を読んでる社会人であれば常識なのだろうが、知らなかったことばかりで非常に勉強になった。どの財閥も結局は銀行が中心にいて、その銀行が MOF 担たてて財務(大蔵)省にペコペコしてたのだとすると「民などいくら金があろうが所詮は官の下僕にすぎぬ」と役人が勘違いしちゃっても無理ないのかもしれないっすね。最初の銀行つくった渋沢は、あっというまに官をやめて野に下った(この表現がすでに官が上という意識そのものだな)のにね。2024/05/18
makimakimasa
13
東京海上や明治安田やキリンやニコンが三菱Gで、三越(元は越後屋呉服店)が三井Gというのも初めて知った。戦前の規模は三井:三菱:住友=7:5:2だったのが戦後6:10:8に変わったという。住友は浮利を追う商社設立がタブーとされ、戦前は貿易を三井に委託していた。三井は銀行の資金力が弱い上に各企業の自主性を重んじ、戦後の企業集団再結集と株式持ち合いが進まず、物産の大合同も遅れた。日立(久原房之介)と日産(義兄で同じ長州出身の鮎川義介が久原鉱業を日本産業と改称)が親戚なのも知らなかった。井上馨が頻繁に登場。2024/02/23
だてこ
10
2021年大河ドラマ「晴天を衝け」で財閥に興味を持って、財閥に関して網羅的にまとめられている本書を手に取った。大河ドラマで出てきた人物(渋沢栄一や岩崎弥太郎や三野村利左衛門)達から現代の企業に続く系譜が分かって面白かった。意外な企業が財閥に属していたりして、今後見方が変わりそう。2021/11/14