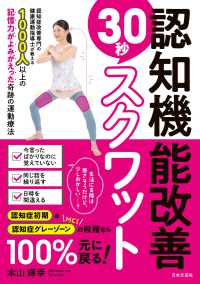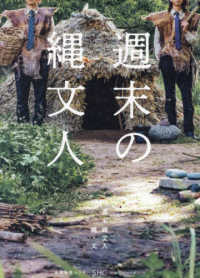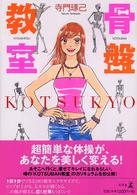内容説明
女性版オスカー・シンドラーと呼ばれる、ポーランド人女性イレナ・センドレル。第二次世界大戦中、ナチス占領下のワルシャワのゲットーから、彼女は2500人ものユダヤ人の子供たちを救い出した。あるときは木箱に入れて、あるときはトラックの積荷に隠して、あるときは下水道をつたって……。連れ出した子供たちは、仲間たちがかくまい、カトリックに改宗させて偽名を与え、ナチスの目を欺いたのだ。子供の命だけは守りたいという親たちの悲痛な願いをかなえるために、彼女たちは自らの命を賭けた。そして、いつか親子が出会えるように、子供たちが自分が誰なのかを知ることができるように、それぞれの本名と出自を記録し、そのリストを必死で守った。ゲシュタポに知られたら、命がないのは火を見るより明らかだったというのに。親衛隊員の気まぐれやお遊びで、ユダヤ人も、ポーランド人も通りすがりに殺されていく世界だった。事実、イレナもゲシュタポに連行され死刑宣告を受けるのだ。生き延びた子供たちは、彼女への感謝を決して忘れることはなかった。この勇敢な女性の活動のすべてを、そして彼女自身の人間らしい生き方のすべてを、見事に描ききった感動的なノンフィクション。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
29
戦時中にユダヤ人のこども達を救うために活動したイレナとポーランドの人たち。「人間らしさ」というものが他の動物には見られないホモサピエンス特有の活動なのだとしたらそれは善なる方向を示すのか、それとも邪悪な方向を示すのかとたまに考える。戦争という極限状況では容易く人間は狂気に支配され暴走し邪悪な人間らしさを示すけれど、それに抵抗するかのように自らの生命を危険に晒しながらも善を示し続ける人たちがいる。希望と絶望。人間の極致のぶつかり合い。願わくばそうした瞬間に善を尊び善を選択できる存在でありたい。2019/11/19
星落秋風五丈原
25
いつか親子が出会えるように、子供たちが自分が誰なのかを知ることができるように、それぞれの本名と出自を記録したリストを作った。ゲシュタポに知られたら、命がないのは火を見るより明らかだったというのに。事実イレナもゲシュタポに連行され死刑宣告を受けるのだ。本当は、親たちは、戦争後の再会を望んでおりその時のためのリストでもあった。だが“その時”を迎える子供たちは殆どいなかった。イリナは勿論偉人であるが、彼女に関わった人々全てが英雄と言っても過言ではない。子供たちを救いユダヤ人の血脈を守った人たちの知られざる闘い。2025/09/24
ケニオミ
19
一人でも多くのユダヤ人を助けようとしたポーランド人女性の物語です。戦時中にユダヤ人を助けたノンフィクションはこれまでに何冊も読んできましたが、助けた数から言ってもぴか一でした。何度も言及していますが、アインシュタインの次の言葉が心に迫ります。「世界は生きるに危険な場所だ。悪いことをする人がいるからでなく、ただ傍観するだけで何もしない人がいるからだ。」見つかれば、自分だけではなく、家族や組織のメンバーに死が訪れることが分かっていながら行動を起こせるのか。何度も、何度も自問してしまいます。是非お読み下さい!2019/04/09
Cinejazz
17
1939年9月1日、ナチス・ドイツのポーランド侵攻に始まった第二次世界大戦中のホロコ-ストと戦後の共産主義に支配された邪悪と恐怖の時代に生きたポーランド人イレナ・センドレル(1910~2008)は、子供の命を救いたい親たちの悲痛な願いを叶えるため、社会福祉局職員の身分を隠れ蓑にして、ワルシャワのゲットーから2500人以上のユダヤ人の子供たちを脱出させて、地下組織の仲間たちの庇護のもとでナチスの目を欺いてきた…。1934年10月、ゲシュタポに連行され、拷問のすえ死刑宣告を受けるも、一命をとりとめた…。 ↓2025/12/07
橘
10
ナチス占領下のポーランド、ワルシャワ・ゲットーから2500人ものユダヤ人の子どもを救った女性がいた。己れの信念を貫く為に、一人また一人と手作業で連れ出し保護してゆく。その彼女を手助けするのも、名も無き普通の人々だった。共産主義のもと、最近まで封印されていた物語が今明かされる。これは多くの勇気ある市民と、生き延びた子どもと、無残に殺された家族と隣人たちの真実の記録である。2020/05/16